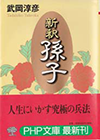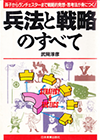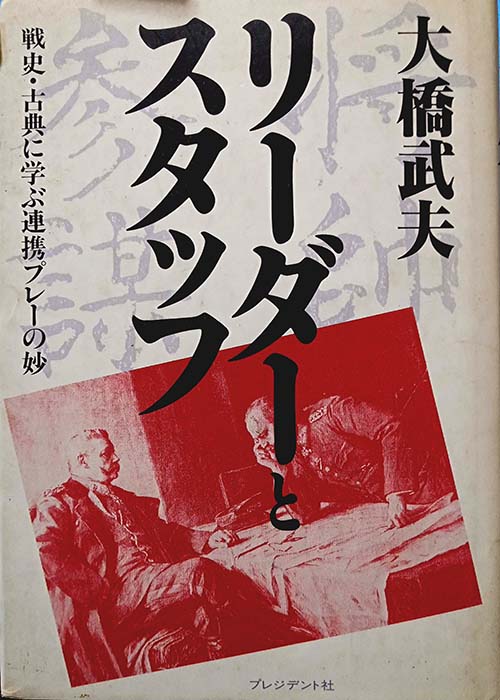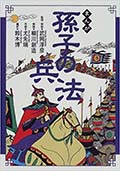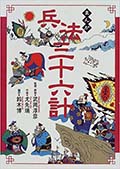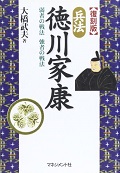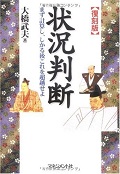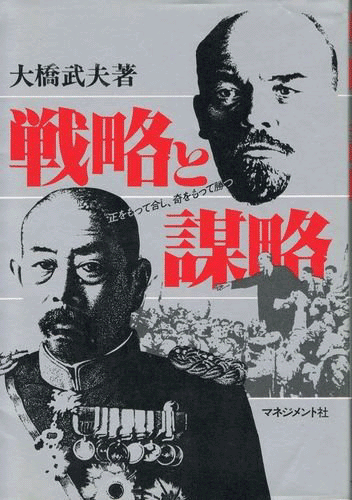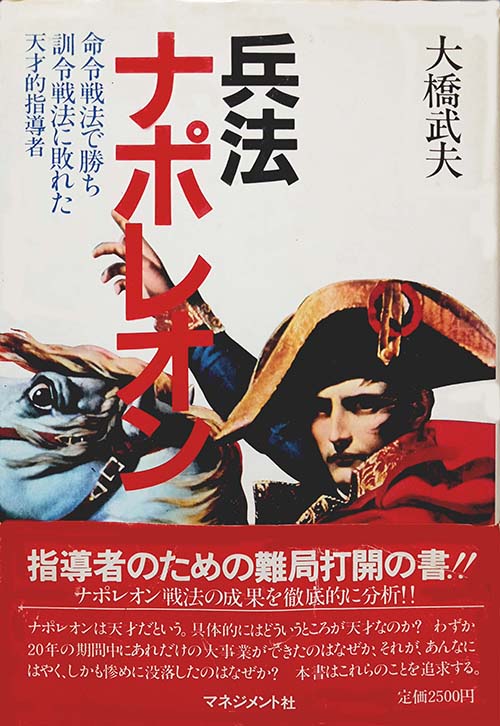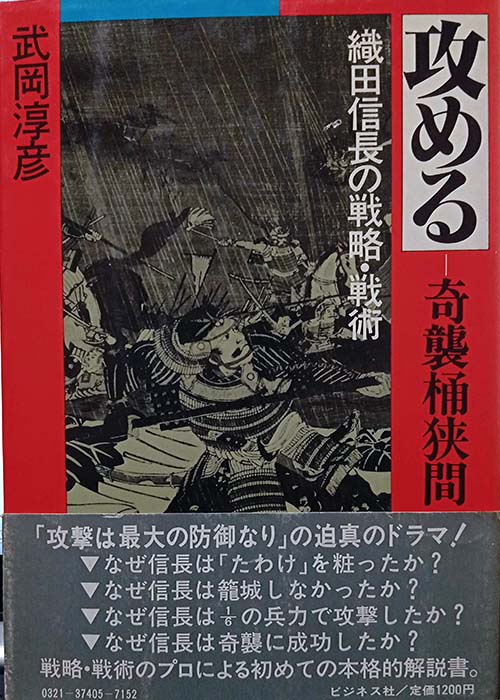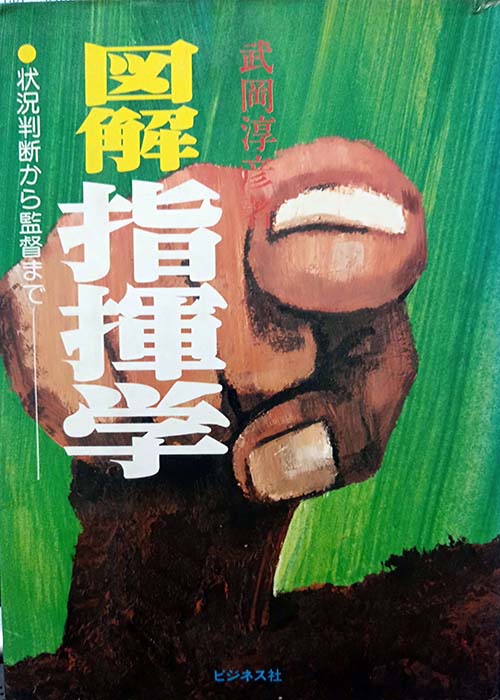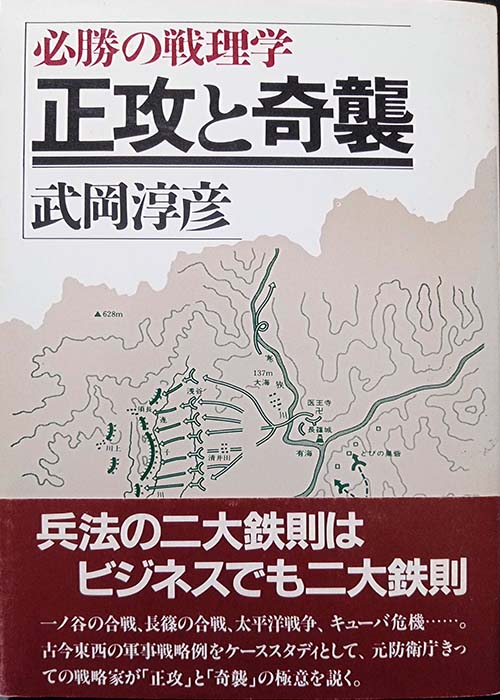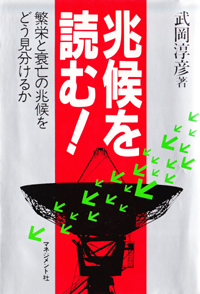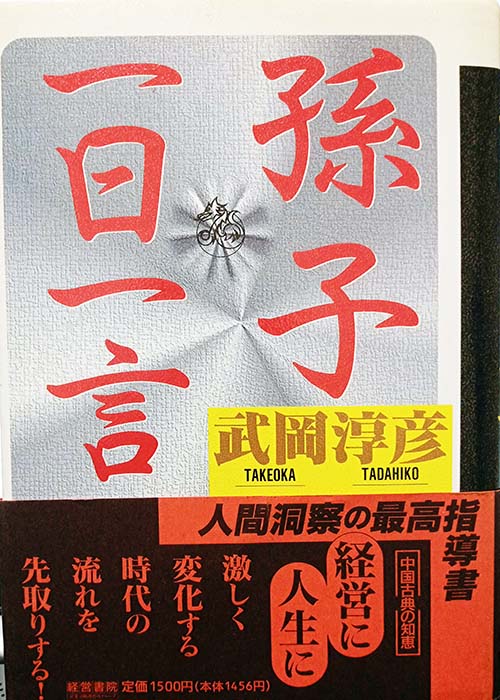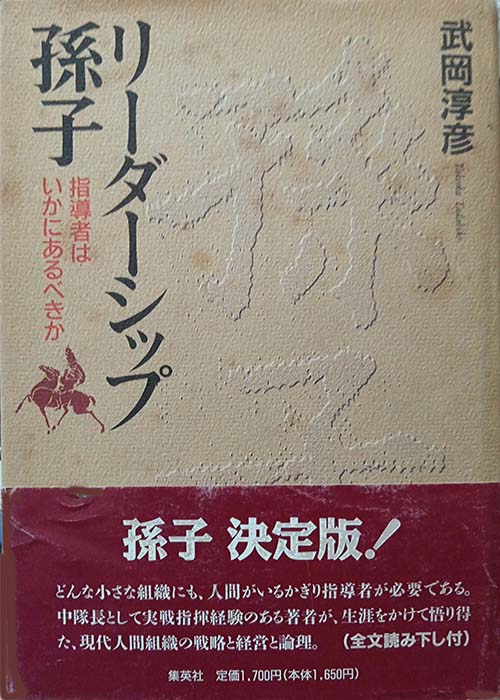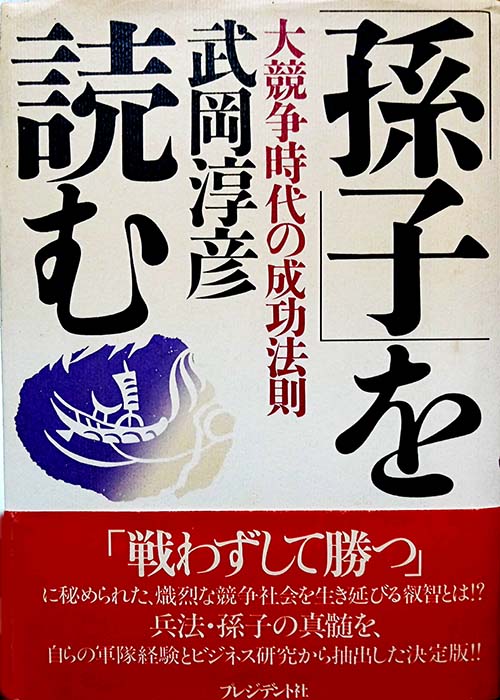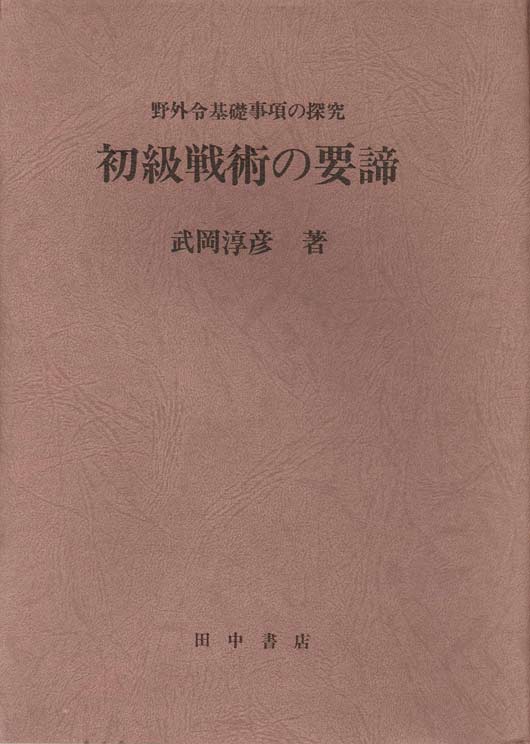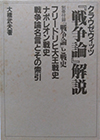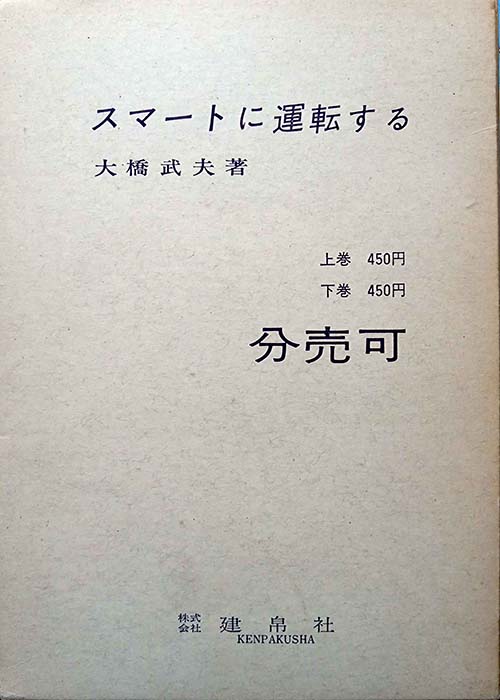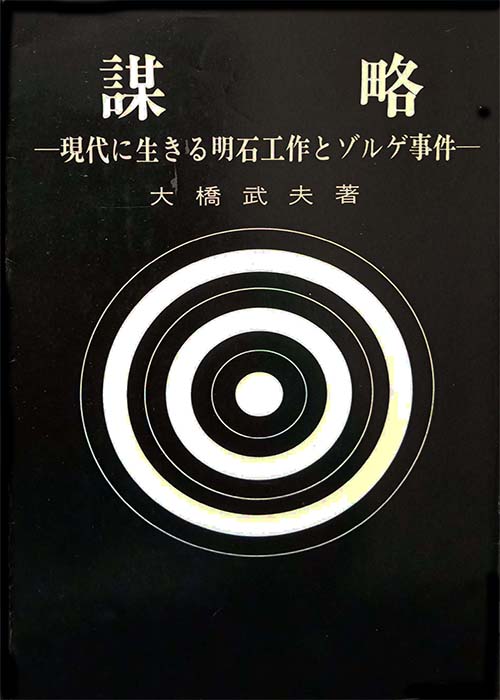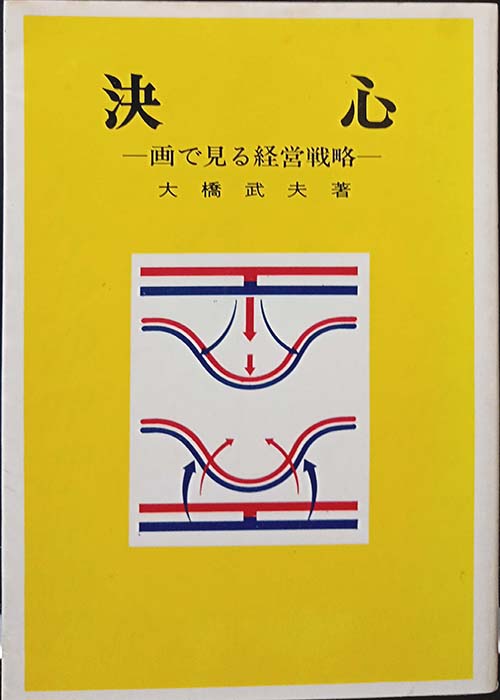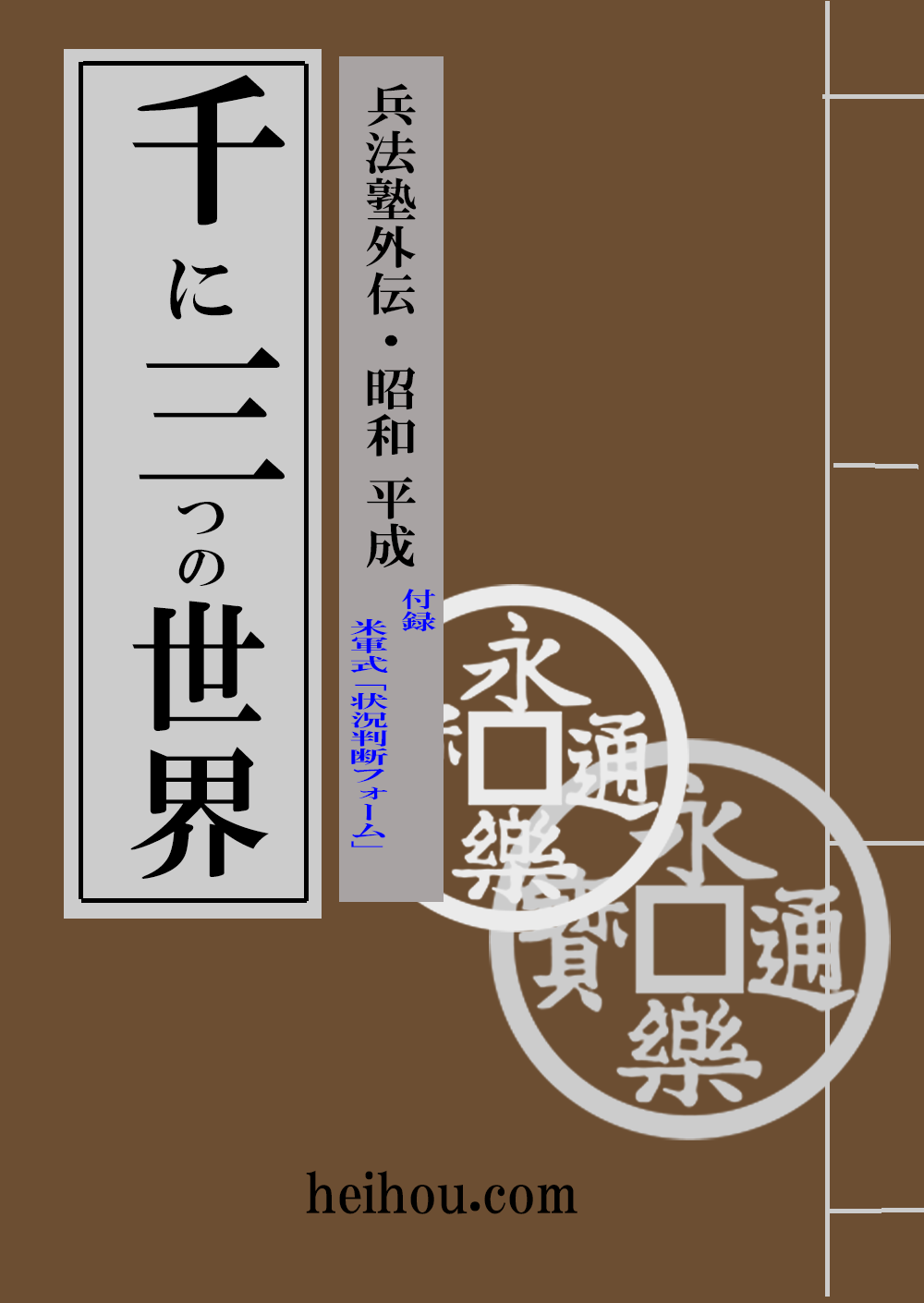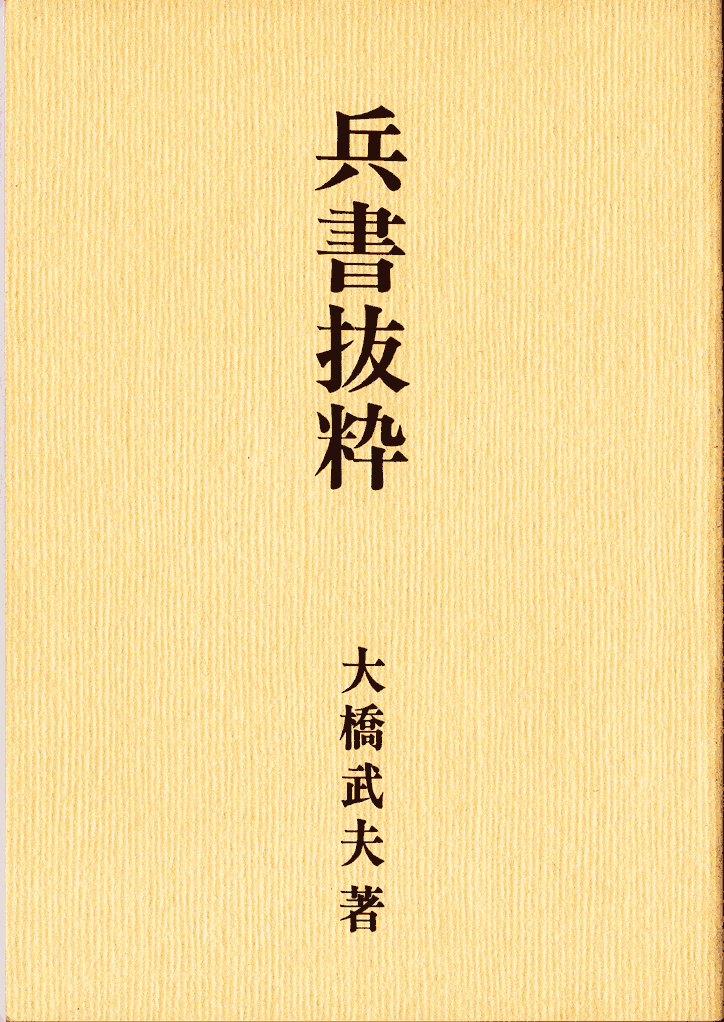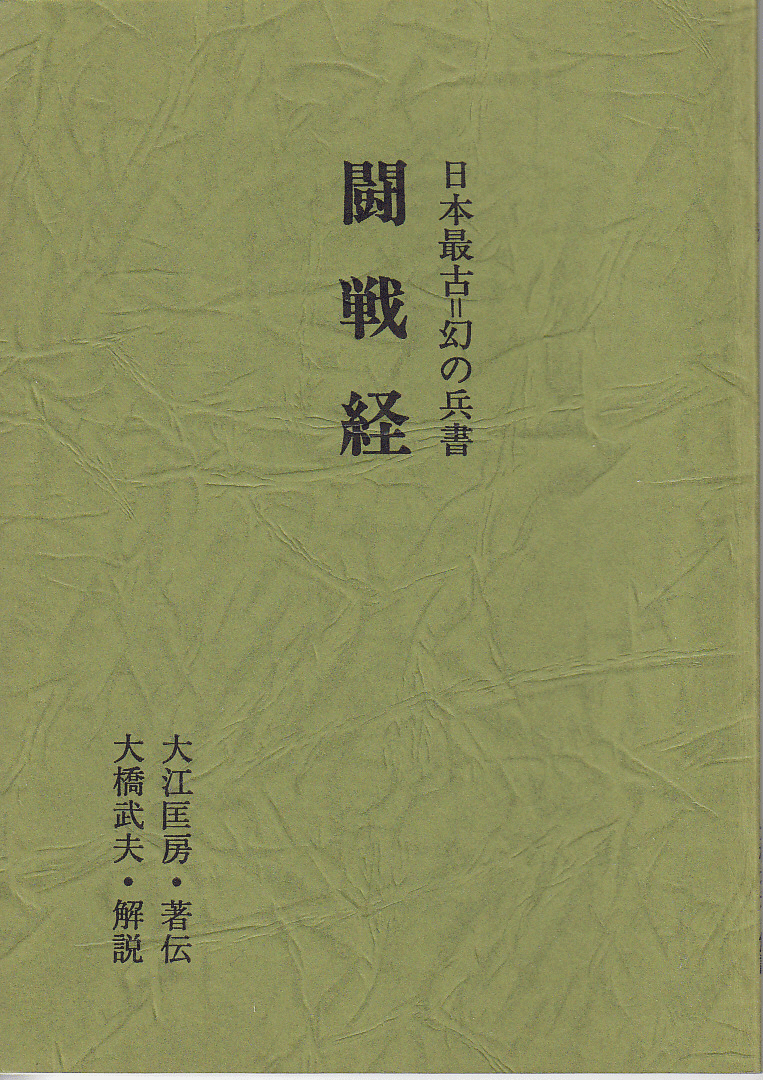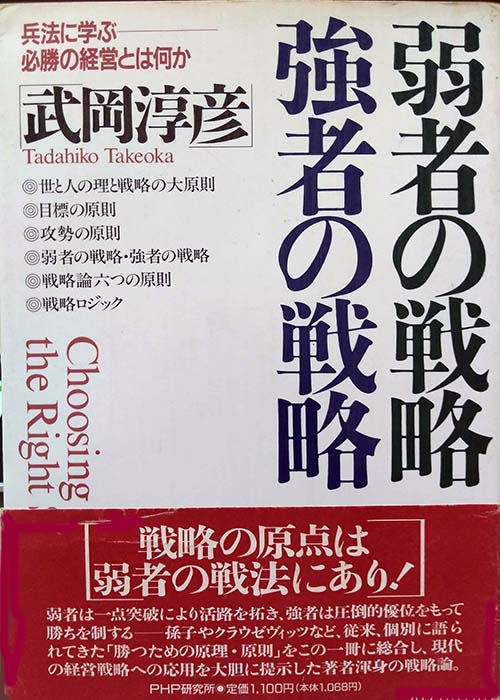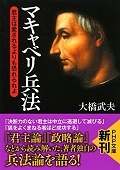『 書は言を尽くさず、言は意を尽くさず。然らば聖人の意は、其れ見るべからざるか。』
-- 易経・繋辞上 --
『 積年の鍛錬自得の心法も、既に古人の書にあり、自らの任にあらず。』
-- 明治の天才剣客・内藤高治 --
『 汝須く一身の安堵を思わば先ず四表の静謐を禱らん者か 』
-- 日蓮大聖人・立正安国論 --
『 聖人まさに動かんとすれば、必ず愚色あり 』
-- 六韜(武韜) --
『 此の時、声無きは声有るに勝る 』
-- 白居易 --
『されば我が弟子等、心みに法華経のごとく身命もをしまず修行して、此の度仏法を心みよ。・・』
-- 撰時抄 --

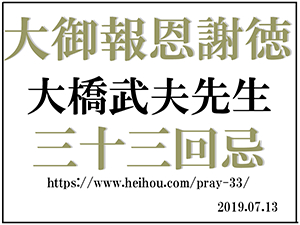




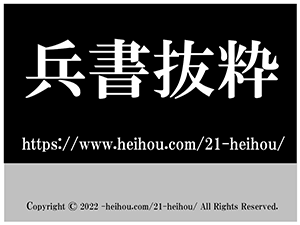
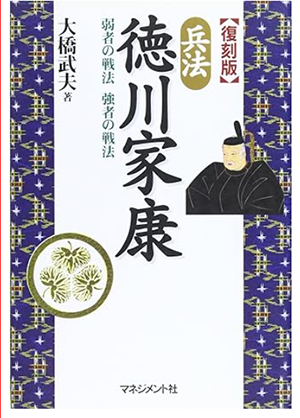

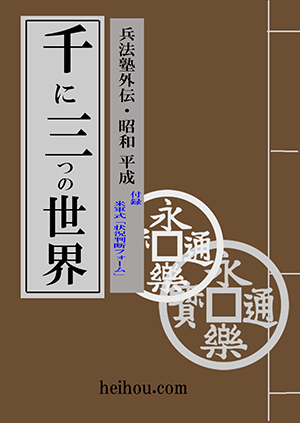
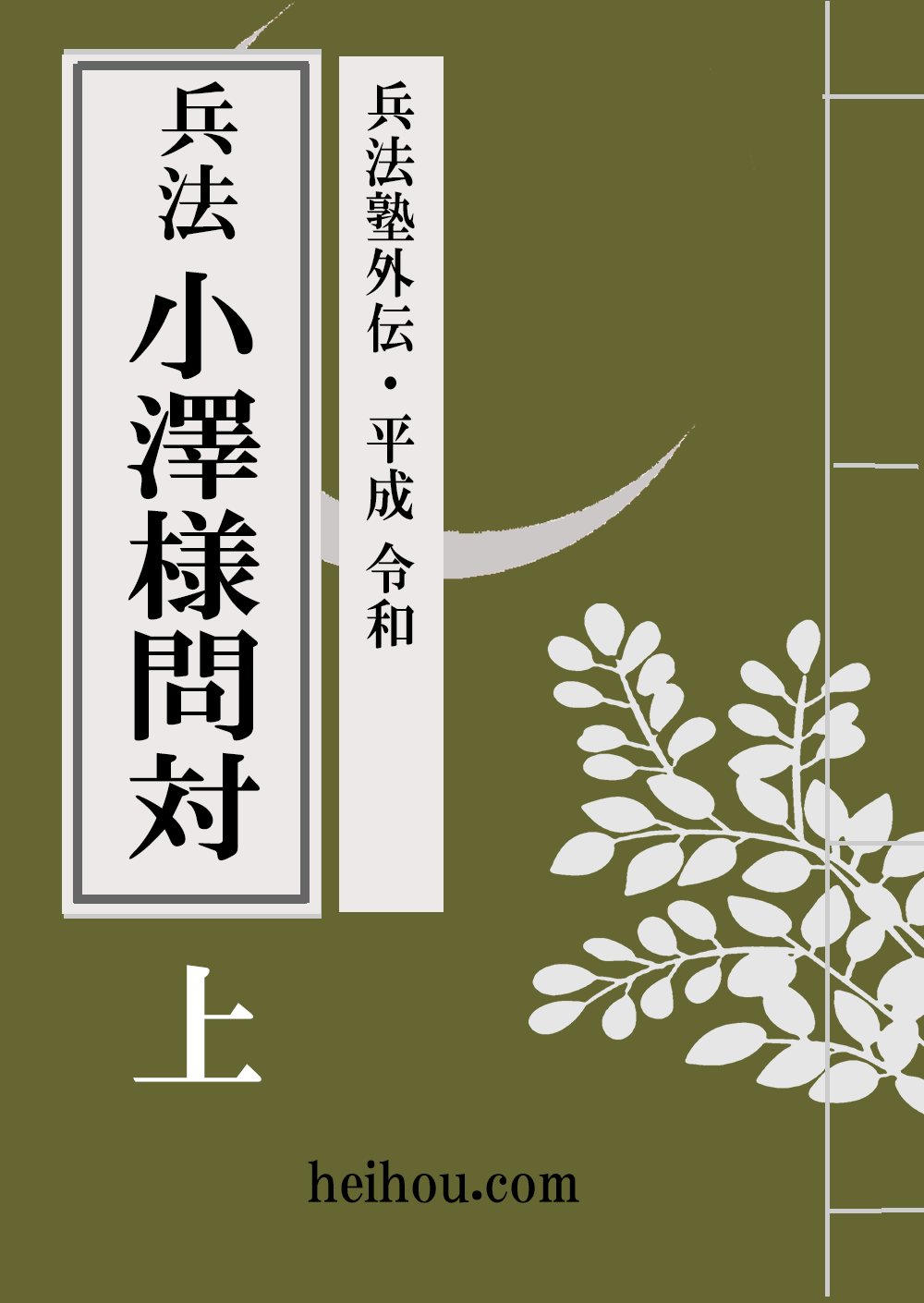
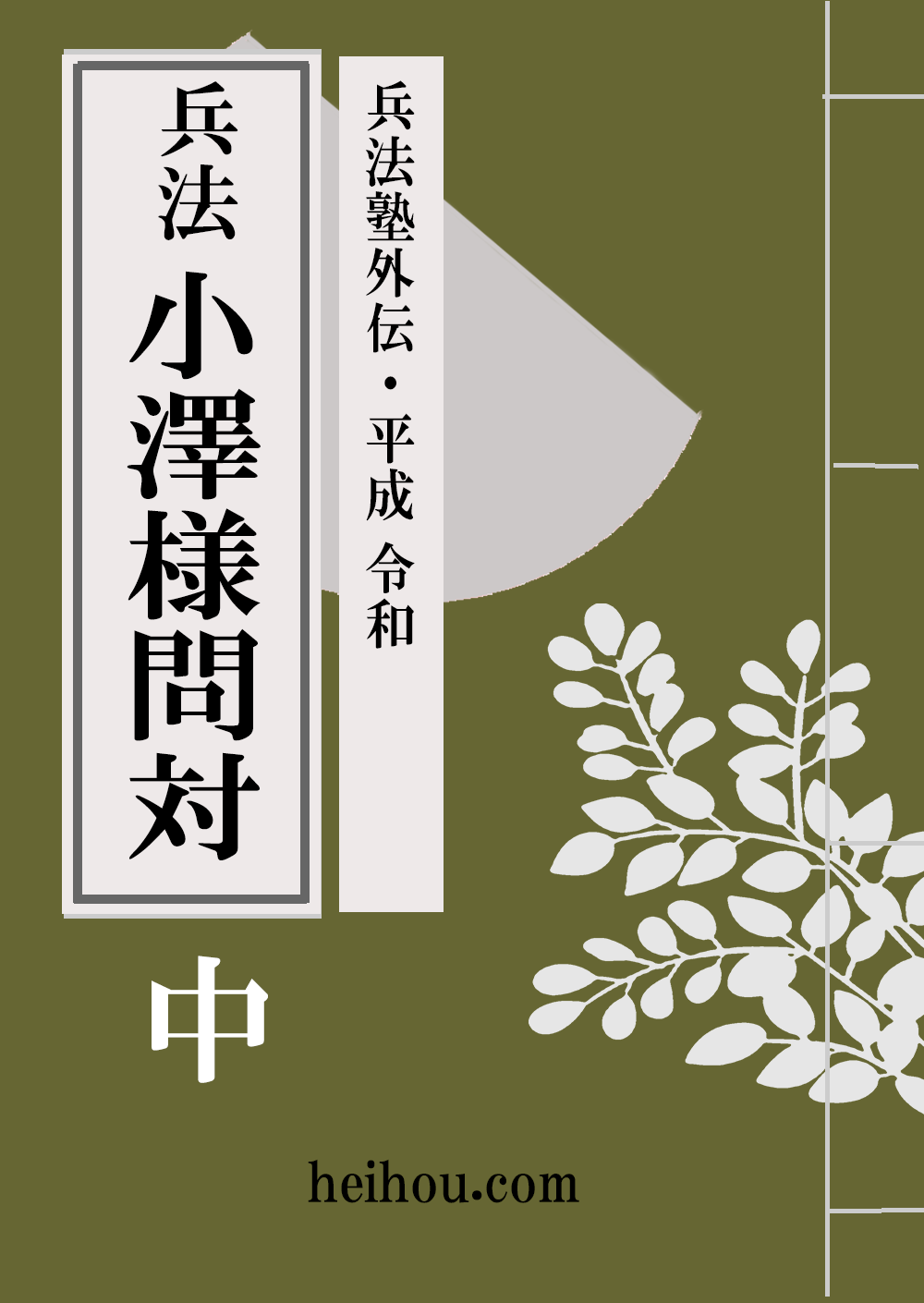
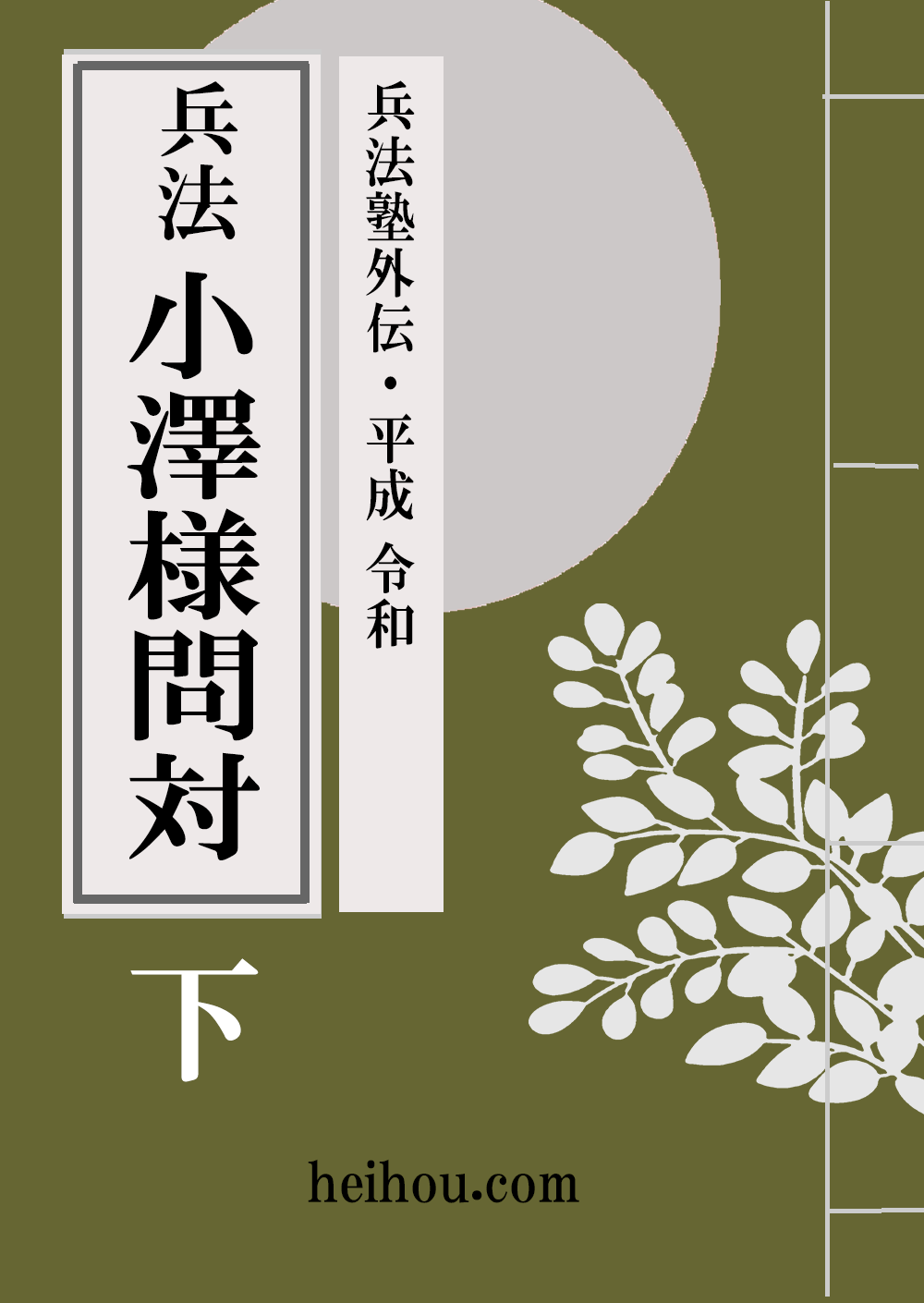
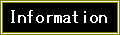

 当時はやっと社会人となって一年くらいたっていた。コンピューター関係の会社であったが当時は東京本社で随意契約で受注した国の行政機関の仕事を人件費の安い地方で処理して航空便で納品していた。そのうち競争入札が加わり売上の半分も占めていた随意契約が三分の一に減り、地方の営業所の人件費を分散(減らす)することになり数名の転勤が決まっていた。既に「孫子」を諳んじ、「史記」を読み、韓信・張良・陳平・蕭何を知っていたが残念ながら先ず役に立ったのは彼らの人間関係に対する身の処し方であった、組織というものは斯くもたやすく人の運命を軽く扱うものかと憤った。その日仕事が終って事務所にひとり残っていたとき著書の後に書いてあった大橋先生のご自宅に電話をしたら大橋先生が出られた。「あのー、先生の兵法経営塾は私みたいな一般の者も参加できますか?。」と尋ねたら、先生は喜ばれて「どちらからですか?○○ですか、○○なら□を作っているところの社長さんが私の本のファンですよ」と言われ、「兵法経営塾の事務局(企業研修会社)から連絡させましょうか?」と言われたが、あまりの突然のことで恐縮して、後でこちらから連絡させて頂きますと言って、事務局の連絡先を教えて頂いた。
当時はやっと社会人となって一年くらいたっていた。コンピューター関係の会社であったが当時は東京本社で随意契約で受注した国の行政機関の仕事を人件費の安い地方で処理して航空便で納品していた。そのうち競争入札が加わり売上の半分も占めていた随意契約が三分の一に減り、地方の営業所の人件費を分散(減らす)することになり数名の転勤が決まっていた。既に「孫子」を諳んじ、「史記」を読み、韓信・張良・陳平・蕭何を知っていたが残念ながら先ず役に立ったのは彼らの人間関係に対する身の処し方であった、組織というものは斯くもたやすく人の運命を軽く扱うものかと憤った。その日仕事が終って事務所にひとり残っていたとき著書の後に書いてあった大橋先生のご自宅に電話をしたら大橋先生が出られた。「あのー、先生の兵法経営塾は私みたいな一般の者も参加できますか?。」と尋ねたら、先生は喜ばれて「どちらからですか?○○ですか、○○なら□を作っているところの社長さんが私の本のファンですよ」と言われ、「兵法経営塾の事務局(企業研修会社)から連絡させましょうか?」と言われたが、あまりの突然のことで恐縮して、後でこちらから連絡させて頂きますと言って、事務局の連絡先を教えて頂いた。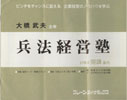 その後、転勤先の事務所で兵法経営塾の資料を手にした。年12回で入会金・年会費合計約40万円。既に数ヶ月分が終っており、今年残りの分を払込んで早速上京した。就学旅行以来二回目の東京は丸の内のホテルの兵法経営塾セミナー会場であった。初めて大橋先生にお会いして挨拶をした、先生は既に70歳は過ぎておられたが大変懇切で無駄な言葉が無く真剣で自信と確信に充ちておられたと思う。私より背が高く、野太い声で、やはり明治生まれの軍人だと感じた。セミナーの参考書・兵書抜粋にサインをされながら、「遠い所をよくおいでましたね、兵法のことはまだ他の人は誰も知らないんだからね。」と話された。グループごとの丸いテーブルの椅子に座って見渡すと、泣きたくなった、二十数名ほどの中で恐らく二十代はおろか三十代の人も居られなかったと思う、傍らの人に名刺を渡し挨拶すると皆、代表取締役〇〇という名刺が返って来た。当然である、ここは経営塾なのである。
その後、転勤先の事務所で兵法経営塾の資料を手にした。年12回で入会金・年会費合計約40万円。既に数ヶ月分が終っており、今年残りの分を払込んで早速上京した。就学旅行以来二回目の東京は丸の内のホテルの兵法経営塾セミナー会場であった。初めて大橋先生にお会いして挨拶をした、先生は既に70歳は過ぎておられたが大変懇切で無駄な言葉が無く真剣で自信と確信に充ちておられたと思う。私より背が高く、野太い声で、やはり明治生まれの軍人だと感じた。セミナーの参考書・兵書抜粋にサインをされながら、「遠い所をよくおいでましたね、兵法のことはまだ他の人は誰も知らないんだからね。」と話された。グループごとの丸いテーブルの椅子に座って見渡すと、泣きたくなった、二十数名ほどの中で恐らく二十代はおろか三十代の人も居られなかったと思う、傍らの人に名刺を渡し挨拶すると皆、代表取締役〇〇という名刺が返って来た。当然である、ここは経営塾なのである。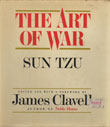
 社名こそ今はやりのコンピューターではあるが営業部以外の何の肩書きのない平社員がとんでも無いところに来てしまったと思った。それも平日に休暇を代え、まだ自分の会社の東京本社にも来たことのないい田舎っぺである。もちろん会社に許可など取れるはずもなく、その後も毎月給料の半分以上を費やして「金蝉脱殻の計」は三年間ほど続くのである。当時は、よく「易」を立てたが正に「天沢履(てんたくり)」(虎の尾を踏むような危ない状況)で虎穴を行ったり来たりした。その内懇意にしていただく社長さんや事務局の方々に気をよくしてセミナーに集中した、何しろ兵法を教えてもらえる先生も学校も他には無いのであるから。昼間は営業兼、納品係りで福岡の街をぐるぐる回っているが、その日の夕方は博多の夜景から羽田の夜景に変わるのである。・・・・・ 武岡先生が亡くなられた後、先生の告別式以来、久しぶりに上京した折、先生ご自宅のご仏前にお参りさせて頂いた。その後友人の結婚式 に参加しての帰り、久しぶりに夜の羽田を見た 。・・・・・ この頃のことを思い出して目頭が熱くなった。「ゆくたびか、鉄(かね)の翼にうち乗りて、都の九天、尚追い止まぬ」であった、誰にも言えず、誰にも知られず、独り歩く東京の街は今となっては絵物語の如くである。セミナーの会場になった帝国ホテルや紀尾井町のニューオータニ周辺は都の歴史物語の舞台でもある。よくセミナー終了後、皇居前の大楠公の下のベンチで今日の講義の戦史を読み返し、幼い多門丸が夜の葛城山を越える姿を思い、熱くなって思わず大楠公を見上た。
社名こそ今はやりのコンピューターではあるが営業部以外の何の肩書きのない平社員がとんでも無いところに来てしまったと思った。それも平日に休暇を代え、まだ自分の会社の東京本社にも来たことのないい田舎っぺである。もちろん会社に許可など取れるはずもなく、その後も毎月給料の半分以上を費やして「金蝉脱殻の計」は三年間ほど続くのである。当時は、よく「易」を立てたが正に「天沢履(てんたくり)」(虎の尾を踏むような危ない状況)で虎穴を行ったり来たりした。その内懇意にしていただく社長さんや事務局の方々に気をよくしてセミナーに集中した、何しろ兵法を教えてもらえる先生も学校も他には無いのであるから。昼間は営業兼、納品係りで福岡の街をぐるぐる回っているが、その日の夕方は博多の夜景から羽田の夜景に変わるのである。・・・・・ 武岡先生が亡くなられた後、先生の告別式以来、久しぶりに上京した折、先生ご自宅のご仏前にお参りさせて頂いた。その後友人の結婚式 に参加しての帰り、久しぶりに夜の羽田を見た 。・・・・・ この頃のことを思い出して目頭が熱くなった。「ゆくたびか、鉄(かね)の翼にうち乗りて、都の九天、尚追い止まぬ」であった、誰にも言えず、誰にも知られず、独り歩く東京の街は今となっては絵物語の如くである。セミナーの会場になった帝国ホテルや紀尾井町のニューオータニ周辺は都の歴史物語の舞台でもある。よくセミナー終了後、皇居前の大楠公の下のベンチで今日の講義の戦史を読み返し、幼い多門丸が夜の葛城山を越える姿を思い、熱くなって思わず大楠公を見上た。
 羽田までの帰りの途中で五反田駅からまだ行った事のない本社ビルを眺める度に東京の陽の傾きの早さを感じた。・・・・。
羽田までの帰りの途中で五反田駅からまだ行った事のない本社ビルを眺める度に東京の陽の傾きの早さを感じた。・・・・。
 初めてのセミナーで大橋先生が、講義の終わりに質問を促された。錚々たる社長さん達の前ではあったが、敬愛する念願の兵法の先生に教示を賜る機会に気負い込み、緊張したまま質問の挙手をした。「孫子に上下、欲を同じくする者は勝つとあります、私は会社では上下の下の人間ですが、先生の言われる兵法経営の会社ではどのようになりますか。」緊張した九州訛りの質問に、大橋先生は丁寧に具体的に労使の賃金体系などの話をされたと思う。その時の内容は舞上っていてはっきり覚えていない・・・。ただ自分の立場と、ここに居られる人達とは立場が異なり、下の人間として上に不信、憤りを感じていることは先生も察せられたと思う。大橋先生の横の席で副塾長の武岡先生は、久しぶりに聞く九州訛りの若者を笑って見ておられた。26年前の光景ではあるが、その時の大橋先生の御姿と武岡先生の笑顔が今もはっきりと蘇るのである。・・・・・時の風に舞い上がった紙くずの様な小さな「凧」ではあったが、二十代のサラリーマン社員では決して見ることの出来ないものを見せて頂き。身分不相応な大変な恩恵を大橋・武岡、両先生より賜った。
初めてのセミナーで大橋先生が、講義の終わりに質問を促された。錚々たる社長さん達の前ではあったが、敬愛する念願の兵法の先生に教示を賜る機会に気負い込み、緊張したまま質問の挙手をした。「孫子に上下、欲を同じくする者は勝つとあります、私は会社では上下の下の人間ですが、先生の言われる兵法経営の会社ではどのようになりますか。」緊張した九州訛りの質問に、大橋先生は丁寧に具体的に労使の賃金体系などの話をされたと思う。その時の内容は舞上っていてはっきり覚えていない・・・。ただ自分の立場と、ここに居られる人達とは立場が異なり、下の人間として上に不信、憤りを感じていることは先生も察せられたと思う。大橋先生の横の席で副塾長の武岡先生は、久しぶりに聞く九州訛りの若者を笑って見ておられた。26年前の光景ではあるが、その時の大橋先生の御姿と武岡先生の笑顔が今もはっきりと蘇るのである。・・・・・時の風に舞い上がった紙くずの様な小さな「凧」ではあったが、二十代のサラリーマン社員では決して見ることの出来ないものを見せて頂き。身分不相応な大変な恩恵を大橋・武岡、両先生より賜った。 大橋先生は、セミナーの折でも、「旧軍でも防衛庁でも本当に「戦略・戦術」を自分の言葉で語れるものは彼(武岡先生)を措いて他にいない」と話され、兵法経営塾・兵法経営研究会の指導を徐々に武岡先生に託されて行った。兵法経営塾は昭和59年の9月まで参加させて頂いた。その後、兵法経営塾のOBで発足された「兵法経営研究会」にも引き続き参加させて頂いて、色々な御支援を頂いた。昭和62年7月、既にもとの〇〇営業所に戻っていたが、突然、兵法経営研究会の事務局の N さんより大橋先生の訃報があり、17日に上京して告別式に参列させて頂いた、その後、御遺族と一緒に、武岡先生はじめ兵法経営研究会の数名の方々と先生の御骨を揚げさせて頂いた。浅学菲才で不遜な世間知らずであったが、皆さんと一緒に先生のお側に置いて頂いたことを心より感謝し、人生最大の誇りに思う。
大橋先生は、セミナーの折でも、「旧軍でも防衛庁でも本当に「戦略・戦術」を自分の言葉で語れるものは彼(武岡先生)を措いて他にいない」と話され、兵法経営塾・兵法経営研究会の指導を徐々に武岡先生に託されて行った。兵法経営塾は昭和59年の9月まで参加させて頂いた。その後、兵法経営塾のOBで発足された「兵法経営研究会」にも引き続き参加させて頂いて、色々な御支援を頂いた。昭和62年7月、既にもとの〇〇営業所に戻っていたが、突然、兵法経営研究会の事務局の N さんより大橋先生の訃報があり、17日に上京して告別式に参列させて頂いた、その後、御遺族と一緒に、武岡先生はじめ兵法経営研究会の数名の方々と先生の御骨を揚げさせて頂いた。浅学菲才で不遜な世間知らずであったが、皆さんと一緒に先生のお側に置いて頂いたことを心より感謝し、人生最大の誇りに思う。
 数年後、上京して武岡先生の書斎 にお伺いした折、机上に大橋先生の小さな「御遺影」があり、小さな「お水」がお供えしてあった。・・・ つい先日の出来事のようにも感じるが、武岡先生は大橋先生のご遺志を受けて兵法経営塾・兵法経営研究会・京都兵法会をはじめ全国に勉強会を主宰され、武岡戦略研究所を立ち上げられた後、平成七年、「国際孫子クラブ」を創始された。第一回の国際孫子クラブの全国大会が平成九年、秋の京都で開催され、大橋先生の兵法経営塾をはじめ、縁の方々が一同に会した。五歳の長男と一緒に参加させて頂き「感無量」であった。その後の第二回目の全国大会を準備して頂いている途中で突然、武岡先生は逝ってしまわれた。その一月ほど前(1999年12月)に上京して先生にお会いしたが、帰り際に玄関で先生が手を差し伸べられた。両手に押戴いて額に当てたが、その時の先生の手の温かさを一生忘れることはできない。・・・18歳の落第生が、三島彦介先生の授業で「孫子」を知り、
数年後、上京して武岡先生の書斎 にお伺いした折、机上に大橋先生の小さな「御遺影」があり、小さな「お水」がお供えしてあった。・・・ つい先日の出来事のようにも感じるが、武岡先生は大橋先生のご遺志を受けて兵法経営塾・兵法経営研究会・京都兵法会をはじめ全国に勉強会を主宰され、武岡戦略研究所を立ち上げられた後、平成七年、「国際孫子クラブ」を創始された。第一回の国際孫子クラブの全国大会が平成九年、秋の京都で開催され、大橋先生の兵法経営塾をはじめ、縁の方々が一同に会した。五歳の長男と一緒に参加させて頂き「感無量」であった。その後の第二回目の全国大会を準備して頂いている途中で突然、武岡先生は逝ってしまわれた。その一月ほど前(1999年12月)に上京して先生にお会いしたが、帰り際に玄関で先生が手を差し伸べられた。両手に押戴いて額に当てたが、その時の先生の手の温かさを一生忘れることはできない。・・・18歳の落第生が、三島彦介先生の授業で「孫子」を知り、