兵 法 塾
兵 法 塾 武岡先生言行録
Military Art from T.Ohashi T.Takeoka
| 兵 法 塾 | ||||||
| 目 録 | 戦 理 | 戦いの要素 | ||||
| 統 率 | 状況判断 | 戦略 戦術 | ||||
| 兵書抜粋 | 戦史 概略 | 名将言行録 | ||||
| 孫子の思想 | 大橋先生言行録 | 武岡先生言行録 | ||||
| 図解 状況判断 | サイトマップ | 兵法経営塾 | ||||
| 将帥と参謀 | 大橋先生著書 | 武岡先生著書 | ||||
| 主宰者プロフィール | 主宰者コメント | Information | ||||
| アフィリエイト | 電子書籍 | WebShop | ||||
| Site情報 | 徳川家康 | About | ||||
『武岡淳彦 先生』言行録
武岡淳彦先生
1922年~2000年、高知県出身、陸軍士官学校卒業後中国大陸出征、中隊長として作戦に従事、貫通銃創三回、個人感状拝受。終戦時、陸軍士官学校区隊長。戦後、警察予備隊入隊。防衛庁要職歴任 、1978年、幹部候補生学校長(陸将)にて退官。大橋武夫先生の嘱望により、大橋先生逝去の後も「兵法経営塾」「兵法経営研究会」「国際孫子クラブ」「武岡戦略経営研究所」等を通して兵法・戦略の理念を全国に普及され、多くのトップマネジメント、ビジネスマンの厚い支持を受けられた。1992年、勲三等瑞宝章。「新釈・孫子」(PHP文庫、2000年)は先生の最後の御著書で究極の「兵法」です。
武岡淳彦先生言行録
〇 目標選定の4要件
目的・目標は兵法の原点兵法は目的を確立し、目標を選定することから始まる。この考えは世の中のすべてのことにあてはまる理論である。
1.目的達成のため決定的価値をもつもの(必要性)
2.能力的に達成可能なもの(可能性)
3.努力の集中力が可能であるもの(集中性)
4.将来への布石となるもの(将来性)
---「目的・目標・手段」(兵法経営塾 1983年資料)より ---
〇 信 条
太平洋戦争開戦直前に陸軍士官学校を卒業し、その後三年半の間、中国大陸の最前線で歩兵連隊の下級幹部として血みどろの戦闘を体験した。その結果得たものは、「たとえ全滅の危機に瀕しても、憶することなく、百方手段を尽くして危機の打開に努力すれば、活路は必ず開ける」との信条であった。 ---「新釈 孫子」(PHP文庫2000年(H12)6月)より ---〇 戦闘指導
「勝つためには、どの障害を除いたらよいかを発想せよ。先に障害を考え、その範囲内で行動を考えるような考えでは絶対敵には勝てぬ。諸君と中隊長の頭の違いはこれだ」私が戦場で中隊の将兵に行なった指導は、常にこの考えであった。---「兵法を制する者は経営を制す」(PHP研究所1983年(S58)3月)より ---〇 勝利への執念
日本人は謙虚と弱気がないまぜになった気持が強く、「弱気人間」の民族性をもつといわれる。戦いでは黒を白といいくるめる強引さと、ブラフ(脅し)も辞さない強気型人間でなければアドバンテージ(先制の利)がとれない。謙虚さと弱気はふだんの個人的つきあいには向いていても、勝負の心には向かないのである。---「兵法を制する者は経営を制す」(PHP研究所1983年(S58)3月)より ---〇 戦場統率
戦場における統率は平時のそれに比べて、異状な特色がある。ふだんいくら立派な統率をしていても、弾がとんでくるところで、卑怯未練な行動、とまではゆかなくても、弾を避けるような動作あるいは勇敢といえないような行為がみられた場合は、部下は心の底からついてゆくのを躊躇するようになるものである。反面、弾がとんでくるところで、勇敢な態度を示せば、ふだん多少いいかげんなところがあっても、あの人はいざというときには頼りになると評価されて、及第点をつけて貰えるのである。このへんの戦場心理をうまく掴んで、指揮することが戦場統率のコツである。戦場の統率は単純でやりやすいが、しかし一たん信用を失えば、百万の言辞を費やしても名誉挽回は難しいのである。--- 「湘桂作戦体験記」( 湘桂作戦戦記出版会1979年(S54)7月)より ---〇 戦場の躾
こう暗くては地形偵察も徒に時間を空費するのみであると思ったので、思い切って中隊を連れて敵陣地の下まで前進することにした。重い装具を攻撃発起位置において身軽になった中隊は、一列縦隊で前進を開始した。周りは一面の田圃である。既に田植は終っていた。畔道に沿って前進していくと、それから下は、一段田が低くなっている畔の境目にやって来た。畔道をとび降りて引き続き目標に向って直進しようと思ったが、ふと思い直して畔道を右に回った。この頃の私は包囲精神が骨の隋まで浸透していたせいか、敵を見たら側背にまわるのが性癖にまでなっていたので、ここは右に迂回した方がよいと直感的に判断し、下の田圃に降りずに畔道を右に回ったのである。そうしたら、私の直ぐあとを続行していた指揮班長が、「夜ですから真直ぐ往ったらどうでしょうか」と一寸不満顔でささやいた。私はぶっきら棒に「これでいいよ」とかまわず進んだ。このなんでもない動作が、あとから考えると私の生命を救うことになったのである。というのは夜が明けてから、重機関銃の分隊長が分隊を連れ、中隊のいる台まで追及するために私が無意識に避けた下の田圃の畔道へ何気なくとび下りたが、その途端轟然と地雷が炸裂し、無惨にも壮烈な戦死を遂げてしまったのである。・・・人の運命はわからないものである。戦場にいると、しばしばこういうことに遭遇するので、誰もが運命論者になりやすい。しかし起きた事故は、その原因を物理的にわりきって考えれば、大抵の場合不用意・不注意に帰せられるべきものが多い。確かに不断と同じようなことをやっていたのに、そのときに限って事故にあったということになると、つい「寿命がなかった」、「運がなかった」ということになりがちである。それだけに、指揮官としてはあくまでも合理的に考え、因果関係を物理的に捉えて教訓とし、あとあとの指揮や訓練に資すべきである。---「湘桂作戦体験記」( 湘桂作戦戦記出版会1979年(S54)7月)より ---〇 指揮官の責任
昭和二十年十月終戦に伴う残務整理が終わると、その足で直ぐ岐阜県下の遺族の家を訪ねて回った。軍刀を外し、階級章をとった軍服姿、その頃の流行語でいえば復員者風のスタイルで、遺族を訪問するのに心苦しかったが、これも中隊長の勤めと、戦地で作った遺族名簿を頼りに、一軒一軒尋ねて歩いた。たまたまこの六月一日の団山舗の戦闘で戦死した中隊本部の連絡係下士官の家を訪れたとき、中風で寝ていた七十三歳になる老父が、「隊長さん、倅は元気でしたか。いつ頃帰ってくるでしょうか」と言われた時は、まさかのこととて、一瞬わが耳を疑った。何の間違いか、この家に限って戦死公報も届いていないし、遺骨も渡されていないのである。家の中には七十を過ぎた老父母が病床にあり、弟さんと近所にいる親類の人が面倒をみているらしい。よほど、「近く帰ってきます。もう暫く待って下さい」と偽って早々に辞去しようかとも考えたが、中国にいる我が中隊も、いずれ遠からず帰ってくることだから、この際はっきり報せておいたらよいと思い、心を鬼にして、「誠に申し上げにくいことですが、お宅の御子息は、もう一年余も前に戦死されているのですよ」といった。その直後に旋風のように起きた遺族達の泣き喚く騒ぎの中で、私は氷のなかに閉じ込められたように堅くなり、身のおきどころをなくした。そうして、穴があれば入りたいような気持を、歯を喰いしばってじっと我慢しつつ、騒ぎの収まるのを待った。どれくらい時間が経ったか分らなかったが、泣きじゃくる涙声も次第にかすれ、近所にいる親類の人たちも駈け付けて顔を揃えたので静かに一礼して説明を始めた。私は厳しかった当時の模様を思い浮かべながら、まず中隊長としての指揮の至らなかったことを詫び、お悔やみを申し上げた。そのあと、この六月一日の戦闘の概要を説明した。それから私も後方にいて「進め進め」とやっていたのではない、その証拠として頸、右足、左胸の貫通銃創の痕を見て貰った。遺族の放心したような顔の中に座っていると、こうでもせずにはいられなかったのである・・・今思い出しても、これまでの人生でこんなにつらかったことはない。人生には、同じ困ったといってもさまざまな困り方がある。だが己の責任に関することは、たとえ心臓が破れる思いをしても、自らの心で突破しなければならない。---「湘桂作戦体験記」(湘桂作戦戦記出版会1979年(S54)7月)---「ビジネスマンの兵法ゼミナール」(にっかん書房1992年(H4)2月)より ---〇 兆候を読む(将来を予測する)
将来を予測するには、予想できる変化を推理し、可能性のある動き(可能行動)を仮説し、その兆候の有無を探求するアクティブな手法(「状況判断」・兆候分析・意義分析)が欠かせない・・・。晴天の霹靂(へきれき)」という言葉がある。晴れた日に、突然鳴り渡って、人々の度肝を抜く"かみなり"のことだ。思いもよらぬことが、唐突に起こる意外性の漢語的表現だ。兆候に関して言えば、兆候がまったく現れずに、いきなり"本体"が降ってくることだ。この「晴天の霹靂」という言葉が麗麗しく存在していること自体、多くのことは皆、前触れがあるという証拠だ。しかし、本当に何の前触れもなく、突如として晴天の霹靂のような出来事が起こるだろうか。 この"かみなり"だって人間が気づかないだけで、実際には雷雲の発生によっておきたのである。「合戦」で不意打ちのことを奇襲というが、これとて討たれる側が油断して気づかなかっただけだ。つまり当事者や一般のものには、まったく突発的な出来事のように思われても、それは技術的(能力的)に予知法が開発されていない、あるいは兆候がわかりにくいだけで、「兆候」は必ずあるのである。・・・本書を書き終わって痛感することは、兆候のもつ意味の重さである。先見洞察が、実は兆候をキャッチするものであったり、背信の兆候が組織活動にこんなに影響を及ぼすものとは思いもしなかった。情報活動を攻撃的にするポイントが、実は兆候であることも書いているうちに確信した。このように兆候は情報活動の中で重要であるにもかかわらず、兆候に敏感な日本人がその効果に気付いていないことは、これまで兆候に関するデータが殆ど出てないことでもわかる。原因はどこにあるだろうかと、執筆中しばしば考えた。結局、そのもとである「情報」に対する意識が、ハードに片寄りすぎているからではないかという気がした。とはいえ、それぞれの専門分野(気象・医療・経済・等々)では決して不勉強ではないし、方法も決して欧米に引けをとるものではないこともわかった。ただそれが、それぞれの専門分野の中で閉ざされたままで、他の「社会公理」として活かされていないところに問題があるようだ。業際化の波も、まだこのソフト面にまではおよんでないわけだ。ともあれ、本書の研究成果は、多くの図書のたまものである。ここに参考文献としてかかげた本の著者の方々には厚く御礼を申し上げる。---「兆候を読む!」(マネジメント社1986年(S61)6月)より ---〇 戦 理
私はかつて中隊長のとき、この適用方法がわからず悩んだことがあった。そのためマニュアル(歩兵操典・作戦要務令)の理解が足りないかもしれないと思って、改めて熟読玩味してみた。しかしそのときは一応わかったような感じはするが、さてそれではこの状況ではどうするかという、状況下の実行要領になると自信のある策案が浮かばない。いろいろ考えた末「実戦を研究してみたら」という、今にして思えばきわめて常識的な、しかも本質的な方法を思いついた。私の手元にたまたま格好の戦例集があったことがこの方法をとらせたのである。私は四冊ある本の中から、歩兵中隊の成功した戦例および失敗した戦例を抽出して研究することとし、毎日夕食後自室の淡いランプ(野戦では電燈がなかった)の下で作業した。方法は、戦例を攻撃篇と防御篇とに分け、ひとつひとつについて、一般状況、戦闘経過、教訓、要図を丹念に写した。それがすむと、ひとつひとつの戦例について、なぜこの場合は成功し、この場合は失敗したかを分析した。そのあと、攻撃で成功するための公約数(二つ以上の数に共通な約数)的な原則はなにか、防御はどうかというように各戦闘行動ごとに、コツともいうべき共通原則を探求した。このように分析を積み重ねた結果、わかってきた原則はなんと、これまで十分理解していると思っていた『作戦要務令』および『歩兵操典』に書かれている原則と、まったく同じものであったのである。このときの私の感激は、四十年経った今でも忘れられない。私はこの理解を胸に秘め次の作戦で活用したが、どんな状況に遭っても、まず迷うようなことはなく、自分でも驚くほどの戦果をあげることができた。※(湘桂作戦において戦功抜群として感状を拝受された。)「戦理」の理解はそれを適用できる状態までもっていかなければ、本当に理解したとはいえないのである。 ---「兵法を制する者は経営を制す」(PHP研究所1983年(S58)3月)---「湘桂作戦体験記」(湘桂作戦戦記出版会1979年(S54)7月)より ---〇 指 揮
私のこれまでの勤務は指揮官か指揮官の補佐職が多かった。私は旧軍と自衛隊勤務がほとんどであったので、この感が特に深い。ところが今度、ビジネス社の依頼で指揮の本を書くことになり、何かこれに関するものはないか、とあたってみたが、驚いたことに、指揮について正面から取り組んだ本というのはないのである。旧軍関係で指揮と名のついた本は、実は指揮ではなくて戦術書である。また、現在民間で出されているものは、どうしたらやる気を出させるか、といったものが多くて、指揮ということに真正面から取り組んだものはほとんどない。民間のものにそういう本がないのはともかく、軍隊か自衛隊にそれがないのは何故だろうか。指揮について書いてあることといえば、作戦要務令や野外令に指揮の要訣と責任について書いてあるくらいのものである。私が自衛隊の最後に勤めた幹部候補生学校の教程にも、指揮の教程がなかったのには迂闊だった。何故、このように指揮というものがはっきりした形でとりあげられないのであろうか。それは指揮という機能が余りにも身近なものであり、古くから組織のあるところでは、意識すると否とにかかわらず、常に行われてきたので、いまさら何を、といった気持ちのせいかもしれない。そしてまた、指揮は、口で言うより、動作として教えたほうがよい、という考えから実技としてとらえ、理論的に指導することをしなかったためではなかろうか。終戦までは、国民皆兵だったため、学校でも軍事教練が行われ、また、多くの人が軍隊で教育を受けた。軍隊というところは、指揮をすることによって成り立っているようなところなので、誰もが自然と指揮の要領について会得して、それが民間に出ても活用できた。ところが戦後は、自衛隊はあっても、志願制だから、多くの人たちが入隊して、指揮を体験することはない。それに学校において軍事教練を行うこともないので、大げさにいえば、戦後は国民全体が指揮というものから遠ざかってしまったという気がする。しかし指揮とは、組織のあるところでは必ず行われているものであるから、企業活動が活発な我が国では、企業を通じて指揮が行われてきたと考えても差し支えないのである。しかも企業は、指揮の良否が結果としてすぐ現れるので、指揮、指揮と呼ばなくても、実行為としては大いに鍛錬されてきたように思われる。しかし、指揮というものが、すべての組織で行われているにもかかわらず、指揮そのものについて、理論的にもはっきりしたものがないということは、やはりそこに無駄な苦労や出さなくてもよい失敗を出していたように思われてならない。かつて旧陸軍で参謀が指揮官を差し置いて指揮権をろう断したと非難されたことがあった。これなどは指揮に対する基本的な考え方が、理論的によく教育されてなかったからではないだろうか。---「図解指揮学」(ビジネス社1980年(S55)10月)より---〇 戦略の原点
戦略の原点は、優勝劣敗の原理からいって弱者と強者の戦略である。しかも本当に必要なのは弱者である。弱者は原理に逆行して勝利を得ようとするからだ。・・・戦略の原点は弱者の戦法であるにしても、強者も弱者同様、戦略が必要であり、戦略の本質を明らかにするとなれば、強者の戦略にもメスを入れることが必要だということだ。---「弱者の戦略・強者の戦略」(PHP研究所 1989年(H元)10月)より ---〇 正攻と奇襲
在官中、戦略・戦術・戦闘に関する著書を四冊も刊行したくせに、「孫子」の「正を以て合し奇を以て勝つ」との兵法の最重要原則を理解していなかった。マニュアルも悪いし、戦略・戦術を教えてくれた教官方もわかっていなかったのも、その一つの理由だ。マニュアルには、正攻法の表れである「集中の原則」と、奇計法の表れである「奇襲の原則」を、それぞれ独立したものとして述べており、この二つの相対立する要因を結合させ、止揚効果を収めることには、旧日本陸軍の教範でも触れていないからである。それが「プレジデント」誌に信長の長篠合戦を書くように依頼され、古今東西の戦例の中でこれ以上の完全合戦はないと思われる信長の作戦指導を書いているとき、「正奇は合一して新しいパワーになる」ことを悟ったのである。しかし、この悟りが二千数百年前、すでに「孫子」によって述べられているのを知るに及んで、改めて自らの思い上がりを鉄槌でたしなめられた気がしたのである。---「必勝の戦理学正攻と奇襲」(PHP研究所 1985年(S60)8月)より ---〇 「管理」よりまず「戦術」を知れ
指揮官(リーダー)はなによりもまず戦理を理解することが最も重要だと思われるが、実情はリーダーの関心が別の方に向いている場合が多い。いうまでもなく指揮官(リーダー)には、①敵を倒して任務を達成するに必要な政略・戦略・戦術の能力 ②所属する組織体を管理する能力 この二つの能力が必要である。ところが私の戦場体験はもとより陸上自衛隊の体験でも意外に第二の管理にウエイトをおく人が多い。戦場で敵と戦っているにもかかわらず、戦略・戦術能力の方をあまり問題にしようとせず、部下の管理の方をやかましくいう人が意外に多いのである。また第一の能力を重視する人でも、いざ作戦となると、積極的に任務達成に努力したか、(責任に対して積極か否か)、あるいは勇敢に戦ったかなどを問題にして、戦いの仕様、勝ち方を二の次にした人が多かったような気がする。私が戦地に赴任したとき与えられた訓示でも、よく戦略・戦術を実戦を通じて学び、敵を多く倒す能力を磨け、とはどの上司もいわなかった。しかし、これは本末を転倒している。「作戦要務令」の綱領にも、「軍の主とする所は戦闘なり故に百事皆戦闘を以て基準とすべし而して戦闘一般の目的は敵を厭倒殲滅して迅速に戦捷を獲得するに在り」と述べられていて、敵に勝つことがすべての基準と示されているからだ。私は四年間の戦場勤務を通じて、部下は管理をやかましくいわなくても、①指揮官が敵弾の中で勇敢に指揮し、②少ない損害で敵に勝つのがじょうず ---であれば、黙ってついてくるものであることを悟った。---「兵法を制する者は経営を制す」(PHP研究所1983年(S58)3月)より ---〇 『機動火力突撃論』
ノモハンでも、ソ軍は日本軍陣地のすぐ傍まで来たが、日本兵が一人でもいれば決して突入してこずに、専ら手榴弾投擲で日本兵の殺傷をはかったといわれる。・・・米軍も同様である。沖縄の戦例を聞いても、彼らは少しでも日本兵が射撃すると、歩兵は後退して砲迫の支援を繰り返し、日本兵の抵抗を破砕してから陣地に入って来たとのことである。旧軍の歩兵操典には、このように最後まで火力で敵を殺傷するという思想は薄かった。旧軍のドクトリンは、敵陣地をある程度たたいて敵がひるんだら、その虚に乗じて白兵突撃を行って目標を奪取しようという考え方であった。すなわち、他国軍のように敵陣地を壊滅するまでたたかずに突撃を成功させようという安上がりの突撃主義であった。その根底には、日本は貧乏だから他国のように弾が豊富でない。弾の代りに肉弾、戦技、精神力で突撃を成功させよう、そのためには訓練をしっかりやってそれができるようにしようという考え方であった。ところが面白いことに、そのドクトリンで訓練した筈の部隊が実施した突撃支援射撃の最終弾に膚接する突撃においても、敵が壊滅的な損害を受けるか、あるいは撤退したあとでなければ殆ど成功していないという事実は、ドクトリンはどうあれ、やはり突撃は火力で壊滅的損害を与えなければ成功するものではないということを教えているのである。この原理を無視して強引にドクトリンを押し通そうとしても失敗するか、たとえ成功しても大きな代償(損害)を払わされるのである。次に近接戦闘に関連して、火力と機動の問題、特に機動とは何かについて考えてみたい。ここでこの問題を提起した理由は、近接戦闘を分析してみると、機動に任ずる連隊の戦闘手段も、実は火力に外ならないのであって、火力と機動の連係というものの、その実態は準備した陣地から撃つ大きな火力と、敵に近迫しつつ撃つ小さな火力とを、いかに旨く連係調和させるかということになるからである。すなわち、機動といっても敵の近くに行って射撃したり手榴弾投擲で敵を破砕することで、結局はいかにして機動部隊の火力を有効に発揮し、砲迫火力等と連係して敵を倒すかということに帰するのである。・・・私の体験した戦闘をふり返ってみても、野山砲や連大隊砲まで含めて火砲といわれるものを集めて射撃した場合、大きな効果を収め得る目標とそうでない目標、すなわち折角多くの弾を使って撃っても、二階から目薬のように余り痛痒を与え得ない目標があった。丁度硫黄島攻略の米運が、あの狭い孤島に約三万トンという膨大な量の爆弾と艦砲射撃を加えたが、地下要塞を構築して潜んでいた日本軍守備隊には、殆ど被害がなかった。このため敵前上陸した三個師団の機動部隊は大きな損害と、約四十日間に及ぶ苦闘によって漸く日本軍を撃滅し、全島を占領したのであった。これは極端な例だが、火力効果の限界と機動の必要性を示した典型的な戦例である。このように上空からの爆撃や後方からの射撃だけでは、地形を利用し工事を施した敵を撃破することができないのである。そこで機動部隊の活動が必要となる。私の体験した戦闘では、機動部隊とは彼我ともに徒歩の小銃部隊であったが、現代戦では普通科と機甲科部隊で、その普通科も徒歩兵は姿を消して装甲車に乗るようになってきた。しかし、編成装備が装甲機動化すると否とにかかわらず機動そのものの本質には変わりはない。すなわち、上空から爆弾を落としても、あるいは後方から火砲射撃を実施しても、すべての目標を直撃してしらみつぶしにしていかない限り、殻を被り、地皺に潜む敵を破砕することはできない。しかしそういうことは、仮に爆弾なり火砲弾が豊富にあったからといって実際問題として実施することは不可能である。そこで敵に近づき、正面から、あるいは側方から射撃し、さらにグッと接近して、手榴弾を投じ、火焔放射機を使って敵を斃していくことが火力戦時代になっても依然として必要なのである。 敵に抵抗の意思と力が残っている場合には、相手が迫撃砲、重機関銃主体の軽装備の部隊であっても突撃頓挫に陥った場合が多く、成功した場合でも大きな損害を出している教訓を重くみたいのである。したがって、まず突入前にできるだけ多くの火力を発揮して、敵に殲滅的打撃を与えるよう努めることが必要である。しかしいかに多く実施したとしても、前述のように守兵を完全に掃蕩することは難しい。そこで突入の必要が生ずるが、突入にあたっては一挙突入を避け、火力を発揮したあと突撃射撃を行いつつ突入し、できる限り損害を少なくして確実な成功を図るようにすべきである。しかしソ軍のように、完全に敵守兵を掃蕩し尽くすまで陣前に停止する必要はなく、ほとんど斃すことができたと判断すれば突入すればよいと思う。いうまでもなく、攻撃は突撃という最後の衝撃行動によって目標の奪取が可能である。この衝撃行動も、現代戦においてはその殆んどを火力によって行い、突入という挺身行為は守兵を斃したあとの最後の最後に行うべきで、強引かつ早急な突入は厳に戒むべきである。ただここで申し上げておきたいことは、このように突入は最後の行為として慎重のうえにも慎重を期するにしても、攻撃に決を与える決定的な行為であることには間違いないので、突入動作はあくまでも厳しく実施すべきであり、またその訓練も厳正的確に行うべきである。それは突入直後の陣地確保、あるいは次の行動への準備行動でもあるからである。最後に、私は現代戦では突撃は動作として実施することもさることながら、むしろ精神的なものとして強調具現すべきではないかと思っている。戦闘では攻撃はもとより防御においても、この突撃精神を失ったら積極主動的な戦闘はできないからである。---「湘桂作戦体験記」(湘桂作戦戦記出版会1979年(S54)7月)より ---〇 方面隊運用序説
本書は飽くまで野外令の方面隊運用を理解するための前提となる事項を解説したもので、それ故に題名も序説としたのである。結論的に私が言わんとすることは、まず作戦を担任し主宰することの重要性を深く認識するとともに、方面隊の運用は師団の相似形的考察ではできないということ。次に、近代戦は、火力戦闘が主体であるので、方面隊運用にあたっては兵站を格別に重視すべきこと。更に、作戦を計画し指導するにあたっては、決戦が焦点であり、決戦指導には明確な戦略理念が必要であること。そして、主動性の確保に努め、追随作戦に陥らないこと等である。そのうえ、我々が設想しているアグレッサーの恐るべき火力戦略をよく理解し、それに太刀打ちできる戦略・戦術を考え出し、それに沿って訓練することが大切である。 実戦において、何が問題となるかを理解するためには、戦史の研究を地道に行うしかない。戦史こそ、方面隊運用を教えてくれる教師である。本書にも、できる限り戦史を活用したが、大部隊の運用を学ばんとする者は、絶えざる戦史研究を心掛けるべきである。---「方面隊運用序説」(陸戦学会1976年(S51)9月)より ---〇 なぜ敗けたのか
創業は易く守成は難しということわざがある。日本陸軍史はこの言葉がそのままあてはまる。建軍から日露戦争までの四十年を、近代陸軍の創業とみれば、その後三十五年は守成だ。守成の末期の舵取りの誤りは、すでに守成の始まりの日露戦争後処理に、その芽がでていた。日本陸軍は十五年戦争に自ら進んでその幕を閉じたようにみられるが、その方向はすでに日露戦争後にきまっていたのである。日露戦争の目的は、ロシアの南下政策を阻止することであったが、それが成功し、さらにその結果南満州に願ってもない大きな獲物を得てみると、こんどはそえを手放すのが惜しくなった。中国マーケットへの進出に、欧州列強に一歩遅れていたアメリカが、日露戦争に勝たせてやったお礼にと、南満州鉄道の買収を要求し、日本がそれを蹴ると他の利権を手をかえ品をかえて要求してきたのをさらに蹴ったのが、日米抗争の発端であった。その結果アメリカと中国をむすびつけることになってしまった。国際関係でも、個人の間と同じように、恩恵を受けたらそれ相当のお礼をするのが当然だが、明治維新で世界と初めてつきあうようになった日本には、その常識がわからなかった。それは戦後の日本にもいえる。日本が現在のように経済大国になったのは、輸出商品で世界市場を席巻したからだ。それでは困るとアメリカやヨーロッパは日本の市場開放を要求してきているが、日本の対応はすっきりしない。そこで相手側は躍起となってたたみかけてくる。いまの日本は経済大国にしてくれたお礼に相応なことをしなければならないときである。それを商慣行と、日本製品の優秀さばかりいっていたら、やがてまた世界から独立する。かつては軍事的成功に酔って失敗の道へと踏み出したが、今度は経済的成功に酔って失敗への道に踏み出していないか、歴史をふり返って自己点検する時機がきている。日本政府に国際社会でつきあっていく常識が不足していたように、日本陸軍にも日本の国の中でどうあるべきかを考える常識がなかった。国も軍も企業も個人も、その常識がなければ仲間とのつきあいができない。国際政治とはやさしくいえばこんなことではないだろうか。つきあいができなければ仲間はずれとなり、やがては独立化し消えていくしかない。それを知ることが大切な教養の基礎ではないかと思う。アメリカの心理学者マズローは人間の欲求を五段階に分け、その第三段階を「帰属と愛情の欲求」としたが、仲間入りしたい、仲間はずれにならない欲求である。これは人間の本能であるとともに処世の哲理である。日本陸軍にこのような教養がなかったことが国家を敗戦の淵に陥れたことはまぎれもない事実だが、国際連盟の脱退に示されたように、国にも他国とつきあっていく常識がなかったことを忘れてはならない。ところでプロ野球を見ていてつくづく感ずることは、日本の野球は技(わざ)の野球、アメリカの野球は力の野球であることだ。力が技に勝ることは、助っ人と称する外人を各球団とも大金を出して、規定数の枠内で入れていることでわかる。日本陸軍の戦略・戦術は技のそれである。技とはわが実をもって敵の虚(スキ)を撃つ技術である。『孫子』はそれを虚実篇第六でのべる。しかし闘争の原理は優勝劣敗、力の強い方が勝つということだ。技は戦術の面では通用しても、戦略の面では通用しない。だから相手との力関係が大差のない戦争、日清戦争やロシアが十分に力を出さない段階で終った日露戦争では勝てた。しかし巨大戦力の相手と四つに組んだノモハンやアメリカとの戦いでは歯がたたなかった。そのような敵にはどうもがいても勝てないことを知らなかった原因は、日本陸軍の戦争研究がアカデミックでなかったからだ。このような技を重視する戦術を重くみるようになって以来、日本陸軍は物質戦力、兵器を軽視するようになった。だがランチェスターの法則では、弱者は一騎打ち型(局地・接近戦)の戦いをするか、武器効率(エクスチェンジレート)をあげる、つまり相手よりすぐれた武器をもって戦うしか方法はないことを教える。となれば国家の経済力、特に工業力が足らないならならば、資材を余り使わなくてもよい兵器の研究開発に努力すべきであった。日本人にはその能力は十二分にあるのだから、精神力の向上とともに、技術度の高い兵器研究の開発にとりくむべきでなかったか。ところが実情は考えられないぐらい「兵器資材」つまり「もの」に対して冷淡になってしまったのである。これも先の戦略戦術同様、戦争の研究がアカデミックでなかったからにほかならない。日本陸軍は終戦のとき、実に六百四十万人いた。しかしこれだけ巨大な組織でありながら、不思議なことに日本陸軍にはその管理の原則つまり組織論がない。一部参謀の専横な振舞や、関東軍の謀略、皇道派青年将校の部隊を使っての要人襲撃の暴挙などは、まともな組織論がなかったからだと言ってもいいすぎではない。アメリカが南北戦争のあと大工業国に成長していく過程で、多民族を擁する組織を、合理性、人間性、システム性、条件性、適応性、生産性の面から追及して組織論を確立し実地に活かした苦労を日本人は知らない。しかも日本人独特の阿吽(あうん)の呼吸や酒場のノミュニケイションによる情報交換や意思の疎通などに頼るだけでは、これからの産業構造の変化のなかで、組織論の不在をカバーしていけるものではない。日本陸軍の組織論不在は、組織は牙(きば)をむく、組織は目的から逸脱する、組織は統一行動をしないものである、などさまざまな欠陥をもつことを教訓として知ることができる。また日本陸軍のリーダーシップは、命令の絶対性を強調するあまり、愛の統率を忘れていた。陸軍に人間的統率がなかったのは、「義は山獄より重く、死は鴻毛(オオトリの羽、きわめて軽いもののたとえ)より軽し」の軍人勅論に基づくが、愛の統率の根源は生命の尊厳、人間尊重の思想である。徳川時代の死の美学を重んずる武士道を継承した日本陸軍にそれを求めるのは無理だったかもしれないが、ここにも現代のリーダーシップを考えるうえで、大きな教訓が残されている。日本陸軍を批判し罵倒するのはよい。だが日本近代史の骨格は、日本陸軍史であるといえるほどの高い比重を占めていたという厳然たる事実がある以上、これからの日本にとって参考とすべき多くの教訓を引き出すことができるのである。それを活かしてこそ過去は現代に役立つのだ。また歴史には絶縁がないのだから、戦後の企業や行政の組織と行動様式の点検と改善に示唆するところも少なしとはしないだろう。太平洋戦争の直前に陸軍士官学校を卒業し、日本陸軍の下級指揮官として太平洋戦争を戦った筆者は、日本陸軍に限りない愛着をもつと同時に、またその後の陸上自衛隊の勤務および退官後の兵法研究を通じて学んだ知識から、さまざまな批判をもつものである。 ---「日本陸軍史百題」( 亜紀書房 1995年(H7)7月)より ---兵書抜粋
「電子書籍」リニューアル編集中です!
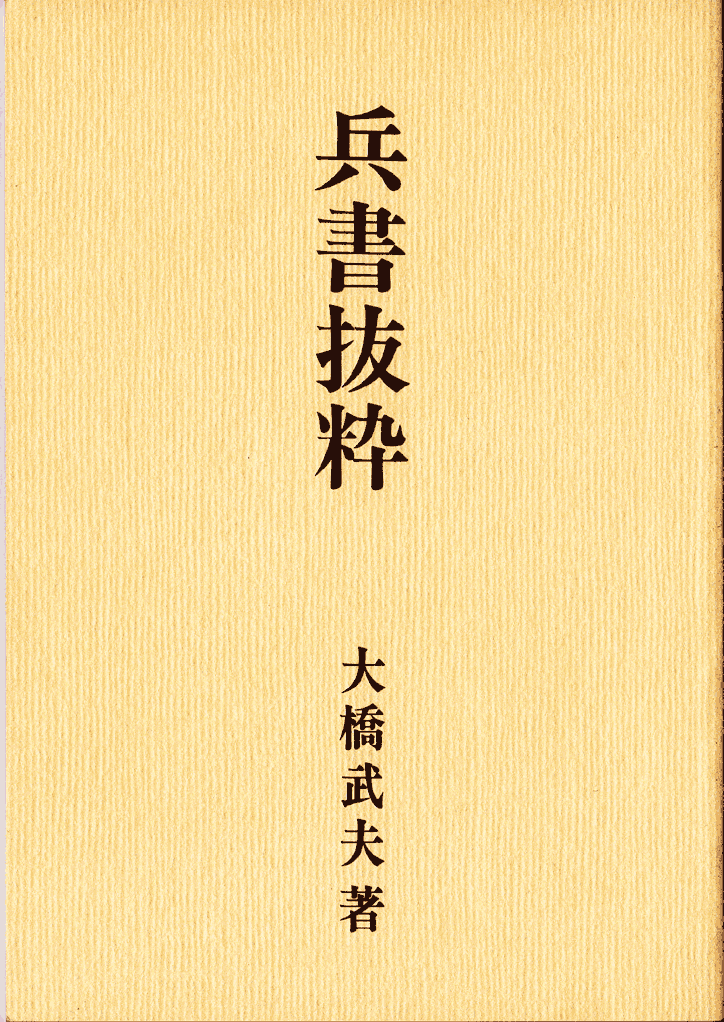
兵書の普遍と真理
兵書には兵法すなわち兵学と兵術が書かれてある。兵学とは戦いの理論と哲学で、兵術とは兵学を実行する術策であり、文字に表現しつくせないものが多分にある。兵法の要は、集団を率いて戦勝を獲得することにあり、「戦わずして勝つ」ことをもって最上とする。戦って勝つための鍵は、我が優勢をもって敵の劣勢を討つにあるが、この優勢はたんに有形の要素だけでなく、無形の要素によってきまることが多い。たとえば不意を突かれた軍はつねに劣勢である。無形の要素は、生命の危険を前提とする戦いの場面において、想像を絶する大威力を発揮するもので、有形の要素の格段の差が有無を言わせぬ猛威をふるうのも、それが人間に絶望感を与えるためでもある。兵法は、本来、性悪説によっている。性善説で粉飾しているものもあるが、これは無理である。とくに統率のためには、将兵の忠誠心や勇敢さが貴重であり、それを養うことに努力しなければならないが、極限状態に陥った人間は、その良識が管制力を失って本能をむき出しにすることを認識し、手抜かりのないように考えておく必要があり、現に信賞必罰を説かない兵書はないのである。性善説を表看板とする日本軍の統帥綱領や作戦要務令も、武士道や軍人精神の修養練磨という事前の準備を強く要請するとともに、厳正なる軍紀(積極的責務遂行心)の必要を高唱し、峻烈なる軍律によって裏づけしている。兵法は時代とともに進化していくものであるが、そのなかに不動の部分がある。それは真理と人間の本質に根を下ろしたもので、百年千年の風雪に堪えて来ており、今後もますます輝き続けていくであろう。本書に抜粋集録したものはこれである。なお、兵書は、時世に恵まれた一人の天才が、多くの人の経験を集めて単純化し、ある主張のもとに編集したもので、たとえば孫子の兵法も、そのすべてを孫武が開発したものではなく、いわば彼は編者である。したがって協力者の参画があったろうし、テクニックに属するものには、伝承者の手による後世の修正加除もありうるわけである。兵法は、たんに戦いの場だけでなく、政治の運営、企業の経営はもちろん、我々が人生を生きがいのあるものにするためにも、そのまま役に立つ。政治も企業も戦いも、要は組織の効果的な運用であり、また、人生は苦難の連続で、我々はこれに打ち勝たねば生きていけないし、打ち勝つことによって、初めて真の喜びを感ずるものだからである。-- 大橋先生著「兵書抜粋」まえがきより --
闘戦経
「電子書籍」リニューアル編集中です!
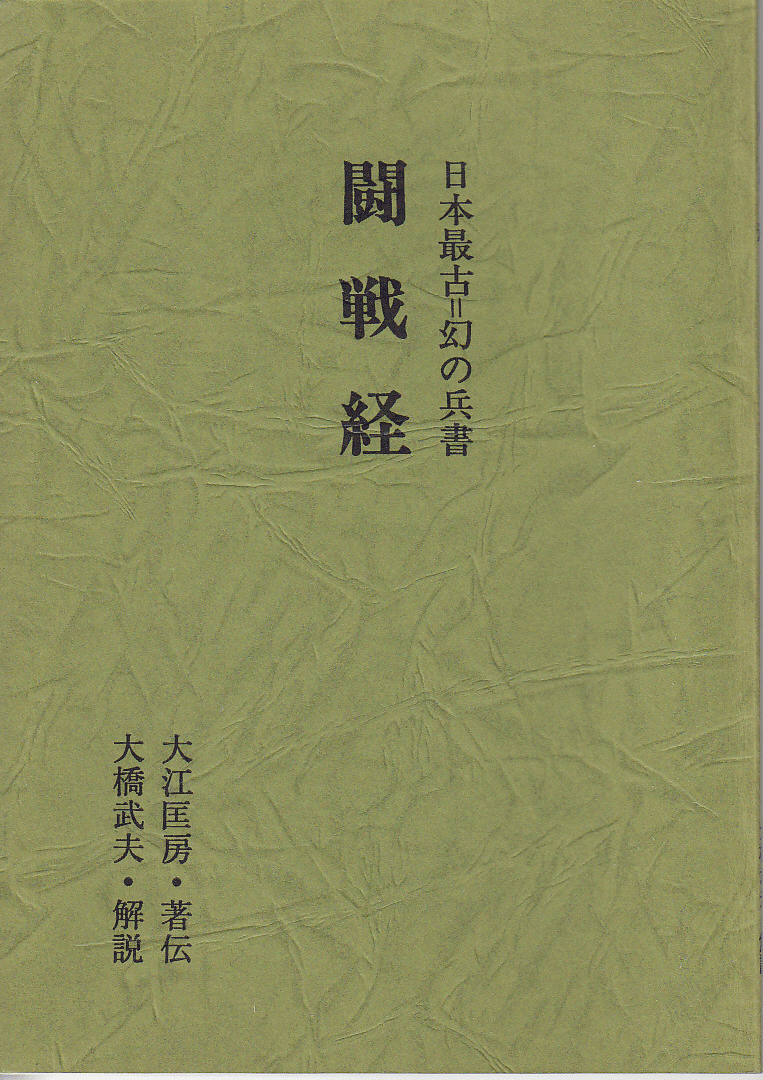
「闘戦経」を世に出すようになった経緯
「闘戦経」は幸いにして先覚の士により、明治にいたってその存在が確められ、海軍兵学校の手に移るにおよんで、昭和九年に木版刷にされたものが若干篤学の士に渡り、さらにその活字化されたものの一本が偶然私(大橋)の所へ来たのである。それは私が東部軍参謀時代の参謀長高島辰彦氏の好意で、戦後「兵法的思考による経営」を研究している私のことを聞かれ、昭和三十七年十月二日に氏秘蔵の一本を下さったのである。氏を中心とするグループはかねてからこの本を研究しておられたようで、篤学の士の訳までついていた。それから十八年後の昭和五十五年十月から、はからずも私はブレーン・ダイナミックス社の前田滋社長の後援により、帝国ホテルと丸の内ホテルで兵法経営塾を開講しているが、熱心な方々が全国から集まられ、ついに昭和五十七年には三年研修生が出ることになった。その結果、今までより高度の兵法研究を行なうことになり、その対象として、中国の「鬼谷子」と日本の「闘戦経」が浮かびあがってきた。いずれも古代の幻の兵書であり、難解である。しかし私は数年前からこの両書を研究していたので、この際これをまとめて本にして教材に使いたいと思い、「鬼谷子」は徳間書店の厚意にあまえて刊行することにし、「闘戦経」は、紙数が少なくて刊行対象にならないため、自費出版をすることに踏み切った次第である。なお大江匡房の文章は現代人にわかりやすいように書き直し、さらに解説と私の考えを付記しておいた。古人の序文に「将来、天機秀発して、後世、しかるべき人に知られるのを待つのみ」とあるが、この八百余年も前の人の悲願が今達成の機を得ることになるかと思えばまことに感慨無量であり、また筆をとる者としてまことに冥利につきる思いがする。なお、私は暗号解読も同様の苦心をして勉強したが、まだまだ不十分なところが多く、結局、私の仕事は「こんな本がある」ということを世の中に紹介するにとどまったようである。私もまた先人の例にならい、将来いつか達識の士が現れて、この本の主張するところをさらに効果的に活用する途を聞かれんことを期待する。なお、あとがきにある大江元綱の言のように、この本は「熟読永久にして、自然に関を脱するを得べし」であり、わからないところはじーっと睨み、繰り返し読みつづけていれば、日本人であるかぎり、いつとはなしにその意味が脳裡に浮かんでくるものであり、読者の不屈の挑戦を念願する次第である。-- 大橋先生著「闘戦経」を考えるより --
電子書籍
「兵法 小澤様問対」
兵法塾外伝・平成 令和
小澤様 !
ありがとうございます。
電子書籍として上・中・下
公開させていただきます。
電子書籍 2024.01.16
| 「兵法 小澤様問対」 | ||||||
| 「兵法小澤様問対」上 | 「兵法小澤様問対」中 | 「兵法小澤様問対」下 | ||||
 |
 |
 |
||||
「兵法 小澤様問対」上・中・下
(兵法塾外伝 平成・令和)
2009年の3月14日に初めて「小澤様」からの掲示板への書き込みがあり、その都度、拙いご返事をお返ししてきましたが、いつの間にか14年も経過して、世相も時代も大きく変化してしまいました。その時勢に応じた大橋武夫先生、武岡淳彦先生の著書やエピソード及び古典、ビジネス書をテーマにした「小澤様」との掲示板での対話が日々研鑽の証となり、個人的にも人生の貴重な足跡となりました。2013年頃より大橋先生の「お形見の書籍」を電子書籍として作成させて頂いていましたが、この度、「兵法塾・掲示板」での「小澤様」との兵法に関するやり取りを、保存と編集をかねて電子書籍として公開させていただきます。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜れば幸甚でございます。
■ 兵法 小澤様問対 上
【9】~【59】2009(平成21)年3月14日~2010(平成22)年6月26日
■ 兵法 小澤様問対 中
【60】~【115】2010(平成22)年7月28日~2013(平成25)年2月17日
■ 兵法 小澤様問対 下
【116】~【178】2013(平成25)年3月3日~2023(令和5)年1月5日
2023年12月
heihou.com
(ヘイホウドットコム)編集・著者
Amazonアソシエイトで著書の一部をご紹介します
| 兵法経営塾 | 統帥綱領入門 |
3 |
4 |
| 戦いの原則 | マキャベリ兵法 |
7 |
8 |
| ピンチはチャンス | 新釈孫子 |
11
|
12
|
| 日本陸軍史百題 | 兵法と戦略のすべて |
15
|
16
|
| リーダーとスタッフ | 孫子の経営学 |
19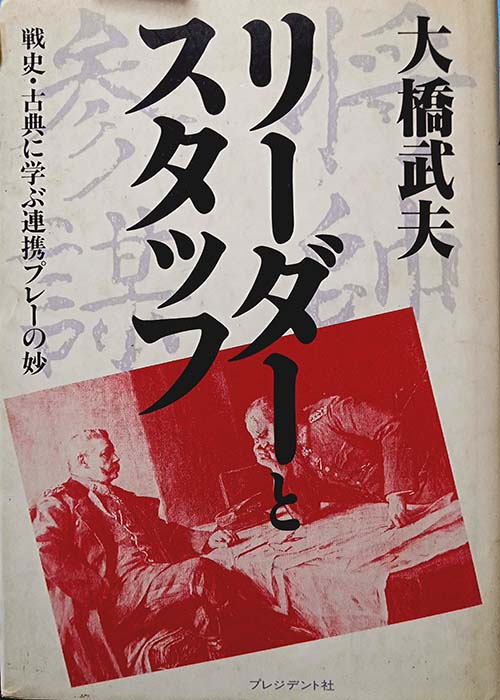
|
20
|
| まんが 孫子の兵法 | まんが 兵法三十六計 |
23
|
24
|
| 兵法 項羽と劉邦 | 絵で読む「孫子」 |
27
|
28
|
| 名将の演出 | 兵法 三国志 |
31
|
32
|
| 兵法 徳川家康 | 状況判断 |
35
|
36
|
| 人は何によって動くのか | 兵法 孫子 |
39
|
40
|
| 経営幹部100の兵法 | 図解兵法 |
43
|
44
|
| 戦略と謀略 | クラウゼウィッツ兵法 |
47
|
48
|
| 兵法・ナポレオン | 参謀総長・モルトケ |
51
|
52
|
| チャーチル | 攻める-奇襲桶狭間 |
55
|
56
|
| 図解指揮学 | 戦国合戦論 |
59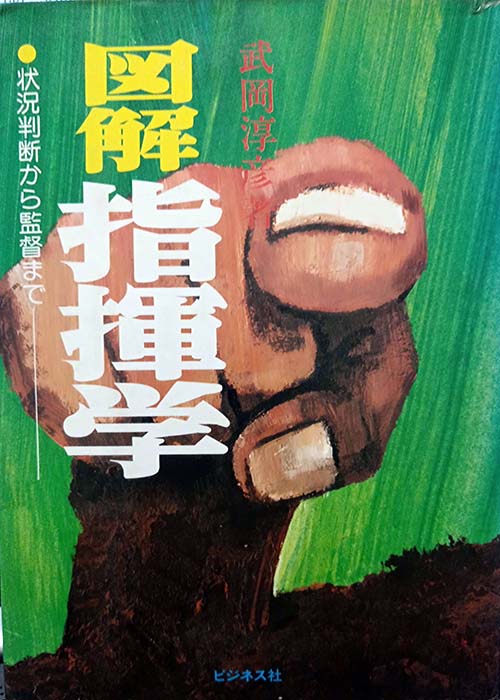
|
60
|
| 必勝状況判断法 | 正攻と奇襲 |
63
|
64
|
| 兆候を読む! | ビジネスマンの兵法ゼミナール |
67
|
68
|
| 孫子一日一言 | リーダーシップ孫子 |
71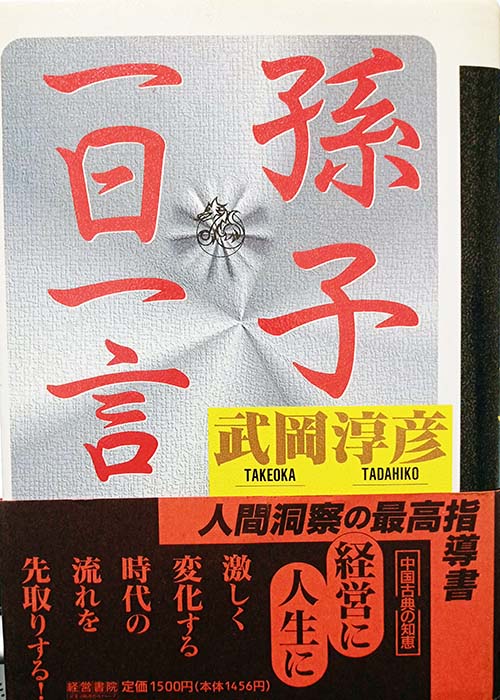
|
72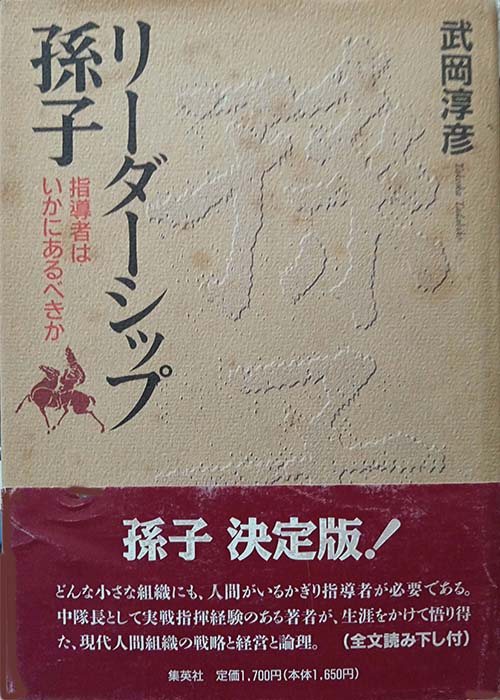
|
| 「孫子」を読む | 湘桂作戦体験記 |
75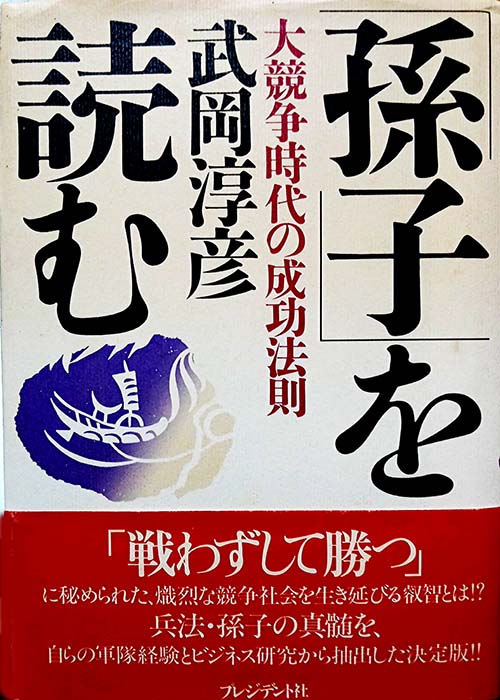
|
76
|
| 初級戦術の要諦 | 方面隊運用序説 |
79
|
80
|
| 統帥綱領 | 作戦要務令 |
83
|
84
|
| 戦争論・解説 | 兵書研究 |
87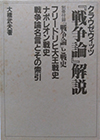
|
88
|
| 図鑑兵法百科 | 兵法で経営する(初版) |
91
|
92
|
| 兵法で経営する(復刻) | スマートに運転する上・下 |
95
|
96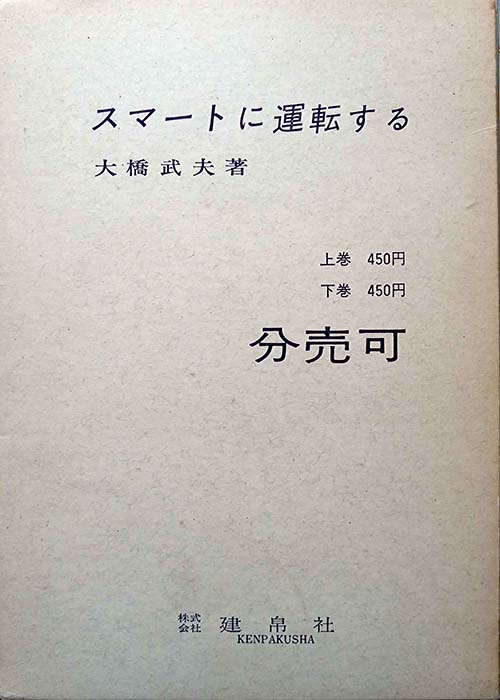
|
| 兵法三十六計 | 鬼谷子 |
99
|
100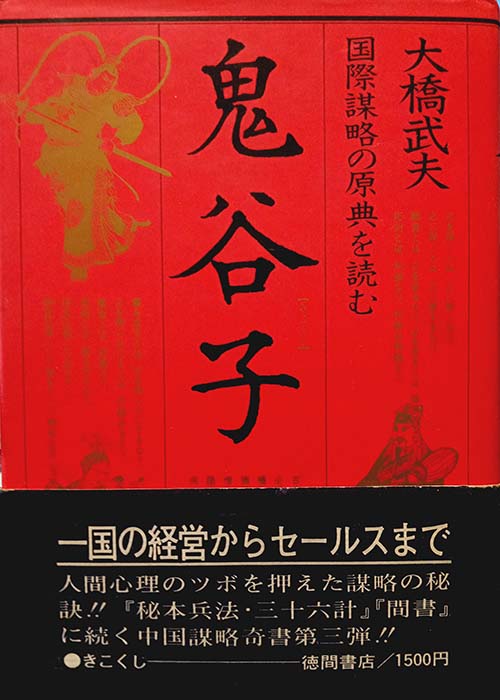
|
| 謀略 | 決心 |
103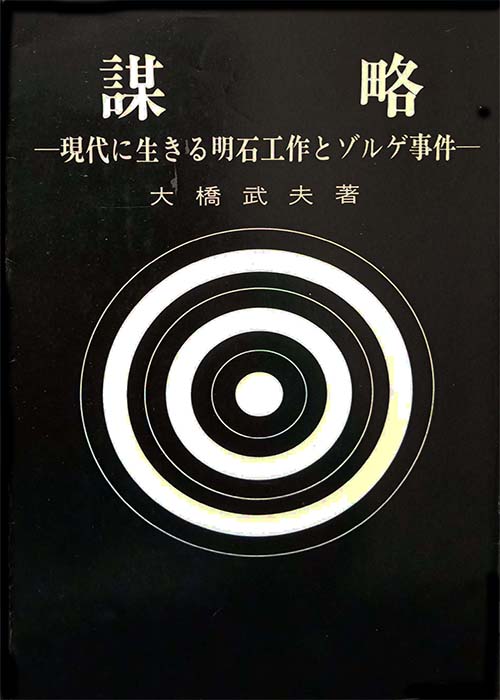
|
104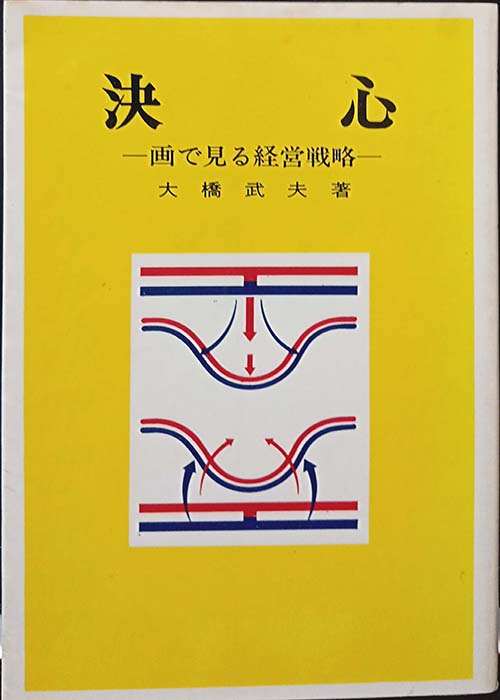
|
| 千に三つの世界 | 兵法小澤様問対・上 |
107
|
108
|
| 兵法小澤様問対・中 | 兵法小澤様問対・下 |
111
|
112
|
©2022- https://www.heihou.com/mobile/All rights reserved.


