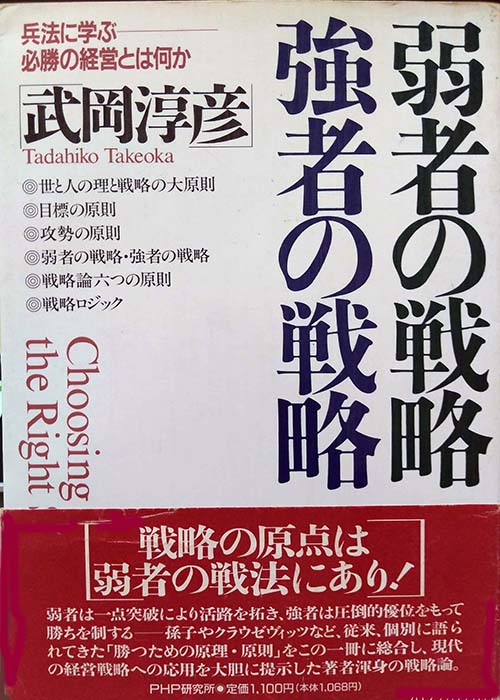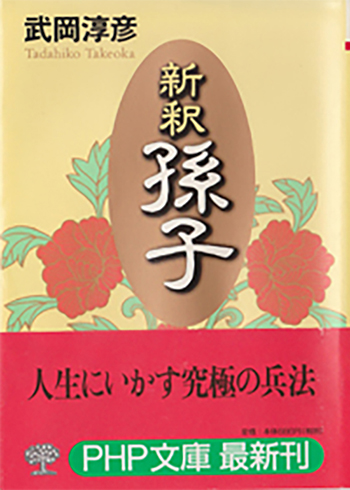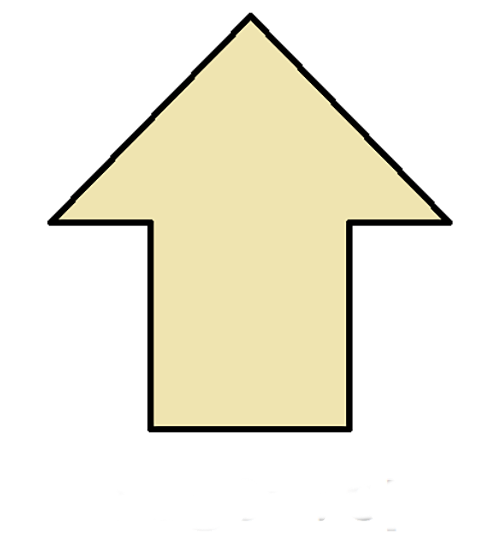兵 法 塾
兵 法 塾 大橋先生言行録
Military Art from T.Ohashi T.Takeoka
| 兵 法 塾 | ||||||
| 目 録 | 戦 理 | 戦いの要素 | ||||
| 統 率 | 状況判断 | 戦略 戦術 | ||||
| 兵書抜粋 | 戦史 概略 | 名将言行録 | ||||
| 孫子の思想 | 大橋先生言行録 | 武岡先生言行録 | ||||
| 図解 状況判断 | サイトマップ | 兵法経営塾 | ||||
| 将帥と参謀 | 大橋先生著書 | 武岡先生著書 | ||||
| 主宰者プロフィール | 主宰者コメント | Information | ||||
| アフィリエイト | 電子書籍 | WebShop | ||||
| Site情報 | 徳川家康 | About | ||||
『大橋武夫 先生』言行録
大橋武夫先生
1906年~1987年、愛知県蒲郡市出身、戦前は第12軍参謀・東部軍参謀・53軍参謀として活躍、終戦後激しい労働争議で倒産した企業を再建、昭和の経済波乱を独特の「兵法経営論」で育て上げられた。昭和55年より「兵法経営塾」を主宰・塾長、その著作・講演・指導は昭和の政界・財界をはじめ、第一線で活躍された多くの人に支持され、平成・21世紀の今日までその名著は版を重ねられています。「人は何によって動くのか」(PHPビジネスライブラリー1987年)は先生の最後の御執筆で古典の奥義・究極の「真理」が顕されています。
大橋武夫先生言行録
〇「兵法」と「戦略戦術」
「戦略戦術」は既に戦う方法であり、戦争論、統帥綱領、作戦要務令は「将軍」や「幹部」の書である。「兵法」はさらに、戦うか戦わないかを決める方法であり、孫子、君主論、政略論は「君主」と「社長」の書である。---「兵法で経営する」1977年ビジネス社「兵書研究」1978年日本工業新聞社「兵書抜粋」1976年私家版より ---〇 兵法は策ではない
「兵法は策である」という誤解が生まれるのは、「孫子」、第一篇(始計)に「兵は詭道なり」とあり、また「戦国策」や「三十六計」などが色々な奇策を並べ立てているためであろうが、 「孫子」、第五篇(勢篇)に「戦いは、正を以て合し、奇を以て勝つ」とあり、正の努力の必要を説いているのを見落してはならない。また「戦わずして勝つ」ためには「戦ったら勝つ」だけの実力を持ち、それをいつでも効果的に発動できる準備を十分にしておかねばならない。このことに気づかず、ただあれこれと策をめぐらすことだけで勝てると思うから、策士策に溺れることになる。兵法はむしろ合理性を追求するものである。なんとなれば、仕事というものは、ただ努力さえすれば成功するというものではない。相手のある仕事、とくに組織を率いてこれに挑戦する場合には、ある種の法則すなわち兵法の理にかなった行動をとることが必要で、これを無視した努力はいかに熱心に推進しても「労多くして功少なし」の嘆を招くことになる。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より---〇 兵書を経営に利用するには
兵書には「敵」という言葉がよく出て来る。これを「経営」に利用される方は、この「敵」を商売仇や競争相手と置き換えられることが多い。しかしこれでは兵書の一番よいところを逃がしてしまう恐れがある。どうか「敵」とは「困難な仕事」と思って頂きたい。---「兵法 孫子」(2005年/PHP文庫)(マネジメント社1980年(S55)10月)より ---〇 兵法「孫子」について
多くの人が「兵法とは策なり」と誤解することは「孫子」の欠点であろう。そのため、わが国における「孫子」の家元である大江家の匡房もこれを心配し、「孫子」は詭譎(きけつ)の書であり、そのままでは、日本では使えないと警告している。---「孫子」は元来わかりやすい本である。それがそう受け取れないのは、後世の加文と補修に際しての乱丁があるからで、慧眼にもこれを見抜いた天野鎮雄氏の明快な卓見には敬服する(天野鎮雄氏著「孫子」参照)。---「原始・孫子」--- 本来の孫子はもっと素朴なものだったのではあるまいか。現代に伝わっているものは分り難い。「容易にうかがい知れないところが奥義の面目であり、孫子の思索の深さを示す貴重なところだ」という説もあるが、孫子は兵書である。学究の書ではなく、実用の書なのである。とくに戦場という厳しい場面で、極限状態に陥って思考力の衰えた人間が使うものは、単純明快で素朴でなくてはならないと思う。前掲の「孫子」はどうも本来のものではなさそうである。文章の筋が通っていないし、各篇のものが混在している疑いがある。不用な語句も多い。二千五百年もの間、風雪を冒して伝承されている間に、後世学者の文字遊び(中国人はこれを好み、巧である)の筆が入り、また誤って編集し直されてこうなったのではあるまいか。たとえば火攻篇の「故にいわく、明主はこれを慮り・・・全うするの道なり」はどう考えても「兵は国の大事にして・・・」の説述であり、ここにあるのはおかしい。人によっては「ここから再び始計篇にかえり、循環してつきないところが、孫子の孫子たる面目だ」などとほめているが、これは贔屓の引き倒しであり、あまりにも文章をもてあそぶものだと思う。孫子のはじめは竹簡、木簡(竹や木の短冊)に書かれ、紐で編んであったので、紐が切れたままで長年月を経過すれば、このように乱丁することはありうる。また、戦闘の具体的手段はもっと多く書かれていたと思うが、これは時勢の変化や武器の進歩などによって通用しなくなる性質のものであるから、消え去っても一向差し支えない。--- 常々私はこんな不遜なことを考えていたが、先年たまたま手に入れた天野鎮雄氏の「孫子」(講談社刊)に、これと同じ意見があるのを発見して、大いに意を強くした。氏の方には学問的な根拠がある。なお、天野氏は学者的良心から「孫子の思想」と遠慮されているが、無知であるがため強さをもつ私は、天野説に勢いを得て「原始・孫子」と題してみた。そしてさらに悪乗りし、先生の文章を台にして、私流のものを書いたのが、次に掲げるもので、我々の孫子はこれで必要にして十分であり、孫子本来の珠玉の光はそのまま輝いていると思うが、古典冒瀆の反省もあるので、篤学の士はどうか「天野孫子」をお読み願いたく、できればさらに「孫子呉子 新釈漢文大系」(天野鎮雄著、明治書院刊)にお進みください。これは完璧である。---「兵法 孫子」(2005年/PHP文庫)(マネジメント社1980年(S55)10月)・「兵書研究」(日本工業新聞社1978年(S53)12月)より ---〇 兵法の極意
兵法の本来は、策ではない。情理をつくした統御と的確なる指揮(合理的な状況判断、勇気ある決心、不屈な実行力)と、かつ教えかつ戦う人間育成によって、組織の力を効果的に発揮させることにある。兵法の要は「組織を率いて勝負に勝つ」ことで、それは多数の人間の命を賭けた真剣勝負である。勝負には相手があり、相手は我を斃そうとする。また組織を率いるには、多数の人間の意志をコントロールしなくてはならないが、意思の自由の本能を有する人間はこれを忌避する。このように「組織を率いて勝負する」ことは、本質的に自分の思うようにならない人間の心を対象にして仕事をしなければならない難しいものである。人の心をつかむには、まずできるだけ合理的に進めて、その理性を納得させておいてから、その後、理論を超越して、その感情を爆発させねばならない。組織を率いて勝負する兵法のむずかしさはここにある。--「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より --〇 「兵法経営塾」
兵法経営塾研修生の名簿を整理してみたら驚いた。兵法経営塾は昭和五十五年十月「兵法経営」をテーマにして、帝国ホテルで開講して以来、今年で四年目になるが、一ヵ年コースであるにもかかわらず、四年間続けて来ている人が十人、三年間が十七人もいる。いずれも活発に発展している企業経営の中枢にあって重責を担っている方々である。この経済激動期において、国の内外にわたって活動し、多忙をきわめている方々が、同じゼミで三~四年の長期にわたって研修を続けるというのは尋常一様のことではない。何がそうさせたか?実のところ私自身にもわからない。塾の内容の一部を紹介して、皆さんのご批判を仰ぎたいと思って出したのがこの本(「兵法経営塾」・マネジメント社)である。--- それにしても、このすさまじく変化する経済情勢の中で、最も多忙な職にある方々が三年も四年も引き続いて参加して下さるということは、思えば驚異に価することである。期せずしてできあがったことではあるが、この事実は、兵法経営塾がわたしの人生中の最大にして、最も貴重な仕事であることを示すものであり、感謝に堪えない。私は七十余年かけて得たものをこの方たちに受け取ってもらい、古今東西の先人たちが命を賭けて築き上げたものを現代に役立て、よりよいものにして後世に伝えてもらいたいと、大いに緊張している次第である。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より ---〇 日本の兵法である
この本は「兵法経営塾」の内容を皆さんにご紹介するつもりで書いたが、出来上がったのを読みかえすと、そのことはもちろん、それ以外にもいろいろなものになっていることがわかる。--- 兵法と言えば直ちに「孫子の兵法」を連想するのが普通であるが、二十一講に記述したように、私の兵法は決して「孫子の兵法」ではなく、まして絶対に策を主とするものではない。私の提唱する兵法は適切な判断にもとづく誠実な努力を主張する「日本の兵法」である。「孫子」「マキャベリ」「クラウゼウィッツ」「統帥綱領」「作戦要務令」など、広く古今東西の代表的兵書を研究し、そのうちから現代の日本人に最も適応したものを選んで、経営的に編成したものである。我々は日本人であるから、私はまず、「統帥綱領」と「作戦要務令」を取り上げたが、敗戦の経験に鑑みて取捨した。そして、これらが国民の忠誠心を基盤として組み立てていて、そのまま経営に適用すれば、とくに部下から裏切られる欠点のあることを考え、性悪説にもとづく合理主義に徹した「マキャベリ兵法」と「クラウゼウィッツ兵法」を取り上げ、それがあまりにも戦闘的である点を緩和する意味で「戦わずして勝つ」の「孫子」を加味した。そして、これらの材料を私自身の三十年に近い社長生活に実用して見た結果が、この本に掲げた「兵法経営」なのである。--- ※「闘戦経」を見直す。昭和五十七年に私家版を出すときには、そのむずかしい文字と文章につくづく閉口し、「実地を知らない学者の文字遊びだ」と軽蔑する感じが、正直のところ、ないとは言えなかったが、しかし今回、一応解釈をマスターした眼で、余裕をもって見直すと、誇大妄想的な記述の裏から、すばらしい真理の言葉が浮かび上がって来、成るほどと関心させられるものが多い。匡房の本音を端的に言えば「我々は先ず日本人としての本来の姿を認識し、それに適応するように「孫子」を取捨せよ。それでないと「孫子」の欠点である策に流れて着実な努力をすることを忘れ、中国のようにいつまでも騒乱を繰り返し、外敵の侮りを受けることになる」と心配しているのであり、現代の我々にとっても傾聴に価する忠言である。この次書くときには、物々しい文句や例え話しを全部削除して、大江匡房のこの本音をつかみ出して、皆さんにご覧に入れ、さらに多くの方々に活用していただきたいと思う。なお、この本には、当時の歴史と人心の動向がにじみ出ていて興味深いものがある。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より ---〇 現代企業の盲点
※ ---「統率」--- 兵法経営塾で講義しているうちに、私は以外なことを発見した。一流企業でも、経営で一番重要な、組織運用の鍵ともいうべき統率について、本格的な構えを持っていないことである。おや!と思って見直すと、一流大学でも統率についての専門講座はないようである。思えばそれも無理のないことで、統率を本職とする軍の幹部を養成するかつての陸軍士官学校や海軍兵学校にもそれはなかったし、まして参謀養成を目的として作られた陸海軍大学校にそれがあるはずはない。わずかに陸軍幼年学校(十四~六歳の少年を教育する陸軍士官学校の予備校)で偉人、名将伝について話されただけである。したがって我々は、指揮と言えば、部隊運動の号令をかけることぐらいにしか、考えていなかった。現代の企業が統率に迂闊であるのも、無理からぬことである。しかし、その結果、統率や指導の理論化ができておらず、とくにその定義がはっきりしていない。そのため、これについて研究しても、理論がよくかみ合わなくて、的確な結論がでないのである。もっとも統率の理論を知らないから、それができないか、というと決してそうではない。統率の理論ができていなくても、数百万の軍隊は整然と戦っていたし、多くの会社はけっこう繁栄している。ただ我々は何となく統率していたのだ。そのため必ずしも的確に人を動かしていたとは言えないし、たまたまこれを立派に実行している人があっても、意識し、理論化されたものではないので、そのノウハウをずばりと人に伝えることができなかった。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より---● 凡人の、凡人による凡人のための「統率と指導」--- 私が自著で、統率の理論化に挑戦したのは、こんなことを考えたためであるが、残念なことに、統率・指導は人間の心に関するものだけに、いくら努力しても、ある程度から先はどうしても理論化できない。しかし、実用的にはある程度までは理論で追求し、原則化することはできるものであり、現在までの残念さは、その程度が可能な限度限度よりはるかに低位にあることで、我々はもっと理論化の範囲を広げねばならないと思う。我々は統率・指導法修得の手段として、多くの偉人たちの実例を教えられた。まず偉人から学ばねばならないが、偉人を真似るのは無意味である。我々がいくら努力しても明天子や織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、のような名将にはなれっこないからである。我々としては誰にでもできる統率の方法を追求すべきであり、「凡人の凡人による凡人のための統率」を求めたい。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より---
● 私は二十年間部隊長として戦地で戦い、二十五年間社長をつとめたが、その間一度も利益と恐怖による統率を意識したことはない。しかしよく考えれば、私の人情統御は陸軍刑法という峻厳な軍律によってサポートされていたし、就業規則に支援されていた。お釈迦様の掌上にいて、千里を走ったと思っていた孫悟空のようなものだったことに気づいたのはこのごろである。---「人は何によって動くのか」(PHP 1987年(S62)7月)より ---
〇 「平和」のもと
各国庶民の交流が「平和」のもとである、この当時、(明治37年・日露戦争当時)アメリカ人は熱狂的に日本贔屓であった。あれを思えば、今日、密接な経済協力関係にあり、日米安保の友好を保持しているのは当然で、先年の太平洋戦争などは、どうしてああなったものか?むしろ理解に苦しむものがある。また大東亜戦争後、スターリンは満州に大軍を進めて「日露戦争の仇を討った」と呼号し、多くの日本人をシベリアに連行して苦しめたが、これもおかしい。日露戦争が日本とソ連の合作であることは、ソ連共産党史上でも明瞭であり、レーニンなどの下で活躍したスターリン青年は、自らの経験で承知しているはずである。国家関係の調整は首脳者間の折衝だけでは十分に行われない。政治家は時に心にもないことを言い、国家代表を意識した者の発言では、本心を伝えあうことは困難で、ともすれば誤解を生みやすい。庶民の直接の交流が必要だと、この頃とくに痛感する次第である。---「戦略と謀略」(マネジメント社1978年(S53)11月)より ---〇 国益本位の「国家戦略」
国家というものの行動は全くの国益本位であり、人々の唱える主義・正義・人道など影が甚だ淡いことである。マキャベリ(1469~1527、イタリア人政治家)は「政治(世界戦略・国家戦略)の中に博愛主義を持ち込むべきではない」と主張し、それを「悪なり」として罵倒を浴びせる人々に対し「しかし、事実であるから仕方あるまい」とうそぶいているが、この本にのせた表の事実はまさにその通りで、各国の指導者は常に「いかにして国益を維持獲得するか」を目指し、その実現手段として「侵略」を選び、合従・連衡の策と弱肉強食の術の忠実なる実行に徹している。しかし「我々も道徳を無視すべきか?」と言うと、それは問題である。我々は歴史の示す事実を素直に認めたうえで、自分の信ずるところに従って、手落ち無く施策を進めるべきで、この事実に眼を覆い無理にきれいごとですまそうとし、あるいは人心の動向の洞察を怠って、非道徳なことをすれば、以外に利口な世論の袋叩きにあって、大きな不覚をとることを覚悟しなくてはならない。---「チャーチル アングロサクソンの世界戦略」(マネジメント社1985年(S60)4月)より---〇 我々は「敵」を見誤っていた
日本は、かねてからアングロサクソンに狙われており、とくにチャーチルの脳裡には、つねに日本が敵として存在していたことの認識が足りなかった。我々の真の敵はアングロサクソンとくにチャーチルだったのであり、これを見誤っていたのがいけなかった。しかし、アングロサクソンに敵対したから第二次世界大戦に失敗したことも事実である。今後の我々は「敵」というものの概念を変え、「敵」とは武力をもって戦う相手ではなく、「理と利を掲げて主張し、妥協をはかることにエネルギーの主力を指向すべき交渉相手である」と思わねばなるまい。「大変むずかしいことではあるが、それは可能である。」たとえば、アメリカとソ連とが経済断交に近い情勢下でも、アメリカの農産物は堂々とソ連に流れている。それが両国共通の利害であるから、さしものレーガンもそれを止めることができないからである。ソ連は食料不足であり、その輸入を止められることは爆弾を落されることよりも怖いのであるが、アメリカは食料が余っており、それを輸出しなければアメリカの農民が困る、すなわち、食料となる農産物をアメリカからソ連に輸出することは、米ソ共通の利益なのである。また、大東亜戦争において日本は、あれだけの武力を行使しながら、東はハワイ、西はビルマまでしか勢力を拡大できなかった。ところが戦後には、なんらの政治力も武力も持たない、従業員二〇〇人足らずの我社のような小企業の製品が世界中をのし歩いている。戦争と違って、この方は相手にも利益を与えるからである。---「チャーチル アングロサクソンの世界戦略」(マネジメント社1985年(S60)4月)より---〇 領土を求める必要はない
日本もドイツも、その国家戦略が目的としたものは、世界の資源と販路の公平なる再配分であり、人間として当然の要求である。しかし、その実現の手段として、武力をもって領土拡大をはかったことは失敗であった。現代は封建時代ではないのだから、資源と販路を求めるために領土を獲得する必要はない。金さえ出せば世界中から資源が集まってくるし、良いものを安く作れば、商品はあらゆる障害を乗り越えて、世界中に流れていく。現に日本の繁栄は、毎年六億トンの資源を輸入し、七千万トンの製品を輸出することにより成り立っているのである。しかし、これを可能にしているものは「世界平和」と「各国が保護貿易主義をとらない」ことであることを忘れてはならない。なお、領土を拡大すると、大きな不利を背負いこむことになるのが現代の特徴である。かつてのように植民地をただ搾取の対象とすることは不可能で、自国の勢力下に入れた以上、そこの住民に平均的な人間生活を保証する必要があり、そのためうっかり未開発国を手に入れれば大きな赤字を負担しなければならない。我々の欲しいのは資源と販路であり、それを手に入れる方法があるのに、わざわざ武力を行使して他国の領土を侵略して恨まれ、そこの住民の生活まで引き受けて苦労するほど馬鹿げたことはない。---「チャーチル アングロサクソンの世界戦略」(マネジメント社1985年(S60)4月)より ---〇 努力は権威である
統率力は、権威の波に乗せると、急速に伝播する。権威のない者がいくら良いことを言っても、人は動かない。統率者はなんらかの意味において権威を持たねばならない。権威には公的権威と私的権威とがある。公的権威とは、部課長、(中隊長・連隊長・師団長・情報参謀・作戦参謀)などの役職に任命されることによるもので、組織の力をバックとする権限によって生じるものである。私的権威とは、個人の身についた能力や人徳によって生ずるもので、任命によって得られるものではない。同じ条件の人間が集まっている集団でも、自然にリーダー格にのし上がるものがある。動物の世界ではケンカに勝ったボスであるが、人間社会では、まめに団体の世話をするものがそうなる。一生懸命に努力している者のいうことは、少々無理でも従わざるをえないのである。努力は権威である。権威を保とうとして無理をし、つねに寸分の隙もなく構えているのは愚かである。部下を持つものは無邪気な隙のある方がよい。また権威はつねに愛情によって裏付けされている必要がある。(「一番いやな仕事を進んで引き受ける者には、自然に権威がつく」・「幹部の権威をつけるための最良の方法は、部下が困っている仕事を解決してやることである」・「批判の対象となった権威は、もはや権威ではない」・「権威を持ち、宗教(愛情・慈悲・いたわり)を失える君主は暴君となる」)---「座右の銘」(マネジメント社 1978年(S53)1月)より ---〇 ピンチはチャンス
この言葉は私が本来提唱してきた「兵法経営論」を貫く根本的な主張である。ピンチとチャンスは同じ姿をしている。したがって、恐ろしいときや苦しいときには、ピンチとチャンスの見分けがつかなくなり、同じ状況でも、名将はこれをチャンスと見、凡将はこれをピンチと見、双方が凡将なら、ともに負けたと思って退却するようなことが起きるのである。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より ---〇 「目的 」と「状況判断」
目的を決めずに「状況判断」をすれば逆の答えがでる。状況判断は、目的を確立して行わなければならない。目的を見失うと、次の話のようになる。「・・・兄弟で驢馬をひいて歩いていたら、無駄なことをする、といわれたので、兄が乗ることにした。しばらくして行き違った人から、あの人は年少者に対する愛情がない、と非難されたので、遠慮する弟を馬上に押し上げたら、礼儀を知らない若者だと叱られた。それではと、二人で仲良く乗ったら、動物虐待だ、と騒がれたので、二人で驢馬を担いで帰ってきた・・・」この兄弟は「驢馬を利用するのか、驢馬を愛するのか?礼儀を主とするのか、年少者をいたわることを主とするのか? 状況判断の目的を確立しておくべきであった。・・・我々は、積極的に目的達成の方法を考えねばならない。人間は、理屈さえつけば、消極策に逃避しようとする本能を持っており、これを理論づけるためにはあらゆる労をおしまない。我々も生産会議で「それはできない」ということを必死になって証明していることに気付いて、苦笑することが少なくない。理論的には、最も有利な方法を求めるべきであるが、現実的には積極的な方法を追求しなければならない。それでないと、苦しいときや危険なときには、結局、何もしないで、自滅してしまう。---「座右の銘 」(マネジメント社 1978年(S53)1月)より ---〇 「状況判断」と「決心」
「状況判断」と「決心」は似ているが、本質的に違う。それは決心には責任をともなうが、状況判断にはそれがない。状況判断は客観的思考であり、決心は主観的な実行意思である。また状況判断は計算であり、決心は創造でもある。株や競輪・競馬では、金を賭けない場合には実によく当る。買ったつもり、売ったつもりで株を追いかけていると、たちまち大きな利益をあげることができるが、いざ金を出して売買すると、さっぱり儲からない。責任をともなうからである。この金を賭けない場合が「状況判断」であり、賭けた場合が「決心」である。決心のむずかしさはここにある。トップでなくては決心できないのもこのためである。状況判断は左右良否などの判断ではあるが、決心のように実行をともなうものではない。「状況判断」は基礎条件が変わるたびに変わるものであるが、そのたびごとに「決心」を変えることはない。すべて状況は刻々変化する。ところが、物事を実行するには、決心から行動に現れるまでに相当の時間と労力を必要とし、これは組織や仕事が大きくなればなるほど大きくなる。そのため、実行は状況変化の波についていけなくなるので、大きな組織のトップほど、上級幹部になるほど、また仕事の量が大きくなるほど、先を読み、時期を画して決心し、その間の状況の小変化は無視する。そうしないと、度々決心を変えることになって、部下はついていけなくて当惑し、その信頼を失ってしまう。状況は連続して流れており、混沌としてはいるが、よく見れば必ず節目がある。連続して押し寄せてくる自動車の流れにも必ず波があり、切れ目があるのと同じである。決心は状況変転の節目を見、決断を以て行う。そして大組織になるほど大刻みにする。状況判断は主としてスタッフ(参謀部・軍師等)やコンサルタント(遊説家・食客・縦横家等)に依存し、あるいはトップ自らが行うが、つとめて民主的にし、衆知を集めて行う。しかし決心だけはトップ自らが厳粛に行い、他に依存することは許されない。依存されても、責任を負えない者にはどうしようもないのである。---「兵法経営塾」(マネジメント社1984年(S59)4月)より --- ● 決心の場におけるトップは孤独である。(ドラッカー)● 側近や重臣から「不決断なり」と見くびられた君主は危ない。(マキャベリ)● いかなる名参謀も将帥の決断力不足だけは補佐することはできない。(クラウゼウィッツ)● 真の叡智とは決断することである。(史記・蒯通の韓信への献策)● 指揮の基礎をなすものは、実に指揮官の決心なり。(作戦要務令)〇 妥協は利益である
妥協は利益である(人間の欲望には際限がない)妥協とはお互いが利益を主張し、折れ合って事を都合よくまとめることである。人間の欲望には際限がなく、人間が求める利益は無限には存在しない。こんな人間が集まっている社会で、限りある利益の取り合いをすれば、互いに傷つくばかりでなく、社会そのものが崩壊してしまう。人間が人間たるところは、このような動物的本能をコントロールする管理能力を持つところであるが、動物に近い人間はこの管理能力が不足するため喧嘩になってしまう。これを国際関係でみれば「戦争」である。戦争ほど愚かなものはないが、古来人間は性こりもなく戦争を繰り返してきたのは情けないことである。情けないが、人間社会はこれからも戦争を性こりもなく続けていくことだろう・・・。● マンネルハイム元帥(フィンランド)の勇気ある妥協で大国ソ連に二度も無条件降伏をしながらも、傀儡政権も許さず、独立を守った。● 遊佐幸平少将(馬術名人)の御馬哲学、「鞍上人なく、鞍下馬なし」というのは、実は「鞍上人あり、鞍下馬あり」の極致の姿である。● 会議とは主張し妥協することである。会議のための十三ヶ条、議長の役割と表の会議、裏の会議が必要である。学者はあくまで真理を追求するもので、妥協は許されないが、我々実際家には好機を逸してはならないという制約がある。いくら良い製品を作っても夏物を秋に売り出しては落第である。したがって「助長補短のできた第三案は、それのできていない第一案に数等優る」● 車の運転は主張し妥協することである・・・事故のほとんどは、交差点などの、彼我意思の衝突するところで、主張と妥協に失敗したときに起きている。● 現代社会において、発展するための必要不可欠の要素とされ、同時に発展を阻害する諸悪の根源とも言われている階級闘争や労使闘争も、遊佐哲学を以てすれば、全面的に歓迎すべきものとなる。したがって、会社に労組がないということは決して自慢にならないし、部下が反抗してくれることは、心の通じあう前工程として喜ぶべきものとなる。● かつて世界に君臨した大ローマ帝国も、その繁栄の歴史の一面は激しい階級闘争と権力闘争の連続であったが、激烈ではあるが、決して枠の外にはみだすことなく、賢明な妥協によってそれを発展の基礎造りにまで結実させた。〇 損して得とれ
仲良く仕事をした仲間同士でも、いざ、その利益を分け合う段になると喧嘩になりがちである。うまく妥協する方法はないものであろうか? それは簡単なことである。相手より多く取ろうとさえしなければよい。四分六分に分けて、六分を取れば嫌われるが、六分を与えれば間違いなく喜ばれる。お互いに六分を与える気持ちになるがよい。もっとも人間は欲張りであるから、自分では六分を与えたつもりでも、第三者からみれば五分以下であろうから、思い切って三分の二を相手にやる決断をしなくてはいけないかもしれない。「三分の二を与えれば、自分の取り分は三分の一しかないが、そんな仕事を三つもすれば、全部取ったと同じになる。彼と共同で仕事をすれば必ず余計に利益をくれるという評判がたてば、良い仕事を持ち込んでくる友人はどんどん増え、仕事に不自由することはない。一つの仕事で三分の二の利益を相手に与えることぐらいはなんでもないことである」---「図解 兵法」(マネジメント社1976年(S51)4月)「立身出世のすすめ」(高木書房 1981年(S56)11月)より ---〇 革新・旧戦法と新戦法
革新(新戦法の採り入れより、旧戦法の追い出しの方が難しい --- リデル・ハート --- )馬に乗って戦う騎士といえば中世ヨーロッパ軍隊の花形であったが、鉄砲の発明とともに、その形の大きさのために、戦闘員としての価値が激減したことは長篠合戦ではっきり見せつけられたところであるが、世界各国とも騎兵隊を捨てることができず、その三百三十年後の日露戦争においても、機関銃の出現により、乗馬しては戦えないことを痛感したにもかかわらず、日本軍騎兵隊が馬から自動車にやっとのことで乗り替え始めたのは、、その三十年後の大東亜戦争直前であった。 1959年につぎ、翌1960年夏に再度来日したアメリカの経営学者ピーター・ドラッカーは、当時の日本の経営者が取り上げるべき緊急事項として①マーケティング・アプローチ ②経営革新 ③長期計画 の三つを提唱し、我々もこれに応え、戦争中の遅れを取り戻すべく、欧米の新手法を採り入れて、とくに経営革新に没頭し、その結果、ついに「追いつき追い越せ」に成功して、今日では逆に欧米産業を圧迫するまでに成長したが、この場合でもやはり、新経営の採り入れよりも旧経営の追放に心を悩ましたのである。いくら優れた技術・機械・経営手法でも、その採用当初は一時的に能率が落ちるから困るのであり、またこれによって地位や利益を失う者との人間関係に苦労するのである。我々の会社でも昭和38年に工場を新築し、設備を一新して、これで万事OK・・・と発展を期待したが、意外なことに、その時から六ヶ月間赤字が続き、会社創立以来のピンチに陥って、蒼くなったことがある。経営革新当座は生産が落ちる、ということを見落としていたからである。17世紀から20世紀にかけて、世界では大革命が続々と行われた。イギリス革命(1649)フランス革命(1788~1794)ロシア革命(1904~1917)などがそれで、いずれもその成立のためには無数の死者をともなう大きな犠牲を払っているが、それは新制度の導入のためではなく、旧制度の追い出しのためであり、その手段として、自国を故意に敗戦においやることまでしている。華国鋒政権は以外にあっさり成立した。しかし未だにどうもすっきりしないのは四人組の残党を追い出しきれないためで、これはなかなか片付きそうもない。自動車会社は下取りをする。決して中古車が欲しいわけではないのであるが、顧客が現在もっている車を追い出して、新車を押し込むためのやむをえない手段なのである。我々の身辺でも、メートル尺は容易に入ってきたが、曲尺と鯨尺は頑として粘っている。新秩序の導入はむずかしい。これによって利益を失う者は必死で抵抗し、利益を得るものは消極的だからである。---マキャベリ--- 旧秩序信奉者に生きる道を与えないと、新秩序は受け入れられない。南北・東西分裂国家統合を妨げる重大因子の一つはこれである。旧秩序信奉者を全員抹殺するようなのは、話は別である。---「座右の銘」(マネジメント社1978年(S53)1月)より---〇 逆境を順境に変える秘訣
一、積極的思考をする気力をもつこと。相撲で土俵ぎわに押し詰められた姿勢は、一般的にはピンチであるが、打っちゃりの機会を狙っている力士にはチャンスである。その違いは本人が「負けまい」と思っているのか、「勝ってやろう」と思っているのかの違いである。
二、なんでもよいから、一つ自信のある能力をもつこと。
「友がみなわれよりえらく見ゆる日よ花を買い来て妻と親しむ」石川啄木の詩である。こんな気持ちになることは我々にもよくある。学校時代は同級生がみな秀才に見え、会社に入れば同僚はみなかなわない有能者である。企業研修に出れば、みな錚々たる連中ばかりで、これでは課長はおろか係長にもなれそうもない。社長になって同業者の会合に出れば、どこの社長もみな颯爽としていて、資金ぐりや技術的行きづまりに苦しんでいるような顔はひとつもない、どう考えても自分の会社が生きのびる見込みなどない。啄木でなくても家へ引きこもりたくなるのが人情である。しかし、ここで一つ、心の置き所を変えて見直してみよう。すべての点で他人より劣っている自分でも、なにか一つくらいは人並み以上のところがありそうなものではないか・・・。どんなことでもよい。自分に人並みなところが一つでもあったらこれを取り上げ、これを人並み以上に育て上げてみようではないか。それで人生は勝てる。
三、身を落すことに勇敢であること。
定年退職で第二の人生を踏み出した人、会社の倒産などで今までの地位と収入を失った人などのその後の様子を見るに、その身の処し方に二通りある。横すべりをして、なんとか今までのレベルを下げないように焦る人と、思い切りよくどん底まで飛びおり、そこからやり直そうとする人とである。崖から落ちた場合、一番苦しいのは途中でなにかに噛り付き、踏みとどまって、よじ登ろうとしているときである。十メートルや三十メートルの崖なら、無理をしないで崖下まで滑り落ち、ゆっくり休み、体力と気力を回復してから、勢いをつけてやり直すことである。人生もこれと同様で、勇気をもってどん底まで落ち、原点に戻ってしっかり足もとを固めてから、勢いをつけて登り直した人々は、途中でもがいているかつての同僚よりも早く崖上に戻り、全勢を利用して前の地位と収入よりも、高い所に飛び上がっている。非常に勇気のいることであるが、昔から言われている「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」である。会社が倒産したり、斜陽化したりした場合には、社長はかつての盛時を思い出して悄然とするものであるが、こんなときには原点を思い出すことが肝心である。創業の時を考えるのである。金も、施設も、人もなかったときのことを考えれば、現在の状態がいかに恵まれているかがわかり、勇気が出る。原点に戻ってやり直すことである。
四、平素から、組織を離れ、肩書きをなくしたときの自分をよく認識していること。
敗戦によって軍が崩壊し、裸でほうり出されたとき。敗戦はショックで、国の運命が心配であり、もちろん自分自身が食っていける見通しもなかった。地位と給料を奪われ、食っていく自信を失って、悄然として町を歩いていた私は、赤ん坊を背負って店頭で奮闘している八百屋の若いかみさんを見て、ハッ!とした。彼女が食っているのに自分が食えないはずはないではないか?と思い、なにか取り柄はないかと、自分の身体をしみじみと見まわしたら、ようやく二つ見付かった。それは身体の丈夫なことと、自動車の運転が出来ることである。日通のトラックの運転手、それが再起の第一歩となった。---「立身出世のすすめ」(高木書房1981年(S56)11月)・「ピンチはチャンス」(マネジメント社1986年(S61)7月)・「 決心十三則」(マネジメント社1987年(S62)1月)---より
兵書抜粋
「電子書籍」リニューアル編集中です!
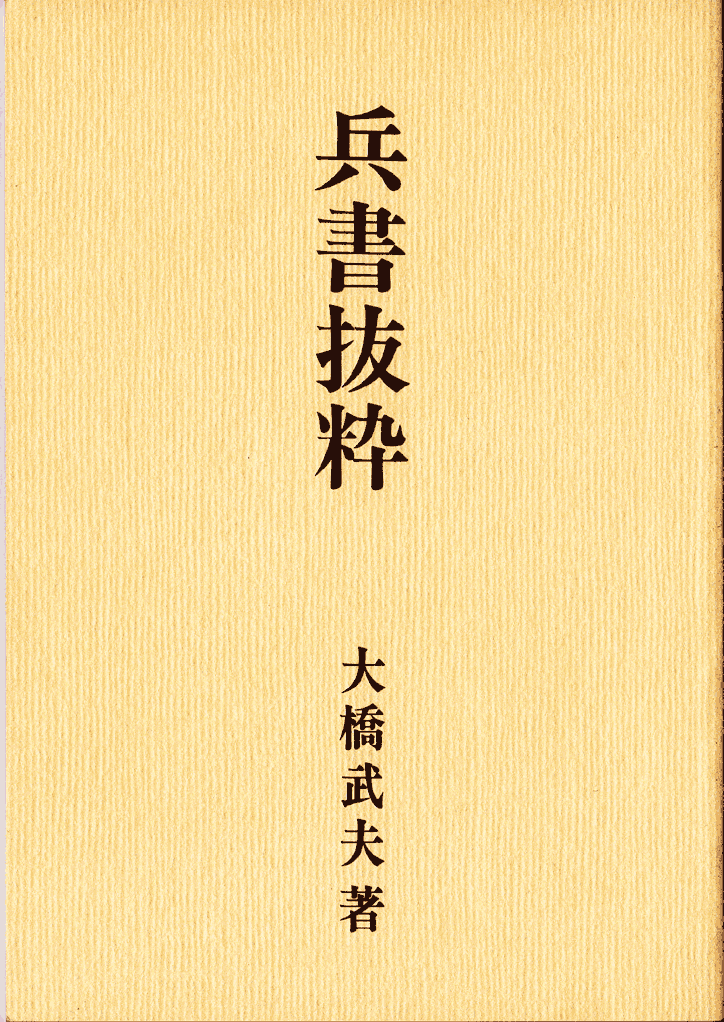
兵書の普遍と真理
兵書には兵法すなわち兵学と兵術が書かれてある。兵学とは戦いの理論と哲学で、兵術とは兵学を実行する術策であり、文字に表現しつくせないものが多分にある。兵法の要は、集団を率いて戦勝を獲得することにあり、「戦わずして勝つ」ことをもって最上とする。戦って勝つための鍵は、我が優勢をもって敵の劣勢を討つにあるが、この優勢はたんに有形の要素だけでなく、無形の要素によってきまることが多い。たとえば不意を突かれた軍はつねに劣勢である。無形の要素は、生命の危険を前提とする戦いの場面において、想像を絶する大威力を発揮するもので、有形の要素の格段の差が有無を言わせぬ猛威をふるうのも、それが人間に絶望感を与えるためでもある。兵法は、本来、性悪説によっている。性善説で粉飾しているものもあるが、これは無理である。とくに統率のためには、将兵の忠誠心や勇敢さが貴重であり、それを養うことに努力しなければならないが、極限状態に陥った人間は、その良識が管制力を失って本能をむき出しにすることを認識し、手抜かりのないように考えておく必要があり、現に信賞必罰を説かない兵書はないのである。性善説を表看板とする日本軍の統帥綱領や作戦要務令も、武士道や軍人精神の修養練磨という事前の準備を強く要請するとともに、厳正なる軍紀(積極的責務遂行心)の必要を高唱し、峻烈なる軍律によって裏づけしている。兵法は時代とともに進化していくものであるが、そのなかに不動の部分がある。それは真理と人間の本質に根を下ろしたもので、百年千年の風雪に堪えて来ており、今後もますます輝き続けていくであろう。本書に抜粋集録したものはこれである。なお、兵書は、時世に恵まれた一人の天才が、多くの人の経験を集めて単純化し、ある主張のもとに編集したもので、たとえば孫子の兵法も、そのすべてを孫武が開発したものではなく、いわば彼は編者である。したがって協力者の参画があったろうし、テクニックに属するものには、伝承者の手による後世の修正加除もありうるわけである。兵法は、たんに戦いの場だけでなく、政治の運営、企業の経営はもちろん、我々が人生を生きがいのあるものにするためにも、そのまま役に立つ。政治も企業も戦いも、要は組織の効果的な運用であり、また、人生は苦難の連続で、我々はこれに打ち勝たねば生きていけないし、打ち勝つことによって、初めて真の喜びを感ずるものだからである。-- 大橋先生著「兵書抜粋」まえがきより --
闘戦経
「電子書籍」リニューアル編集中です!
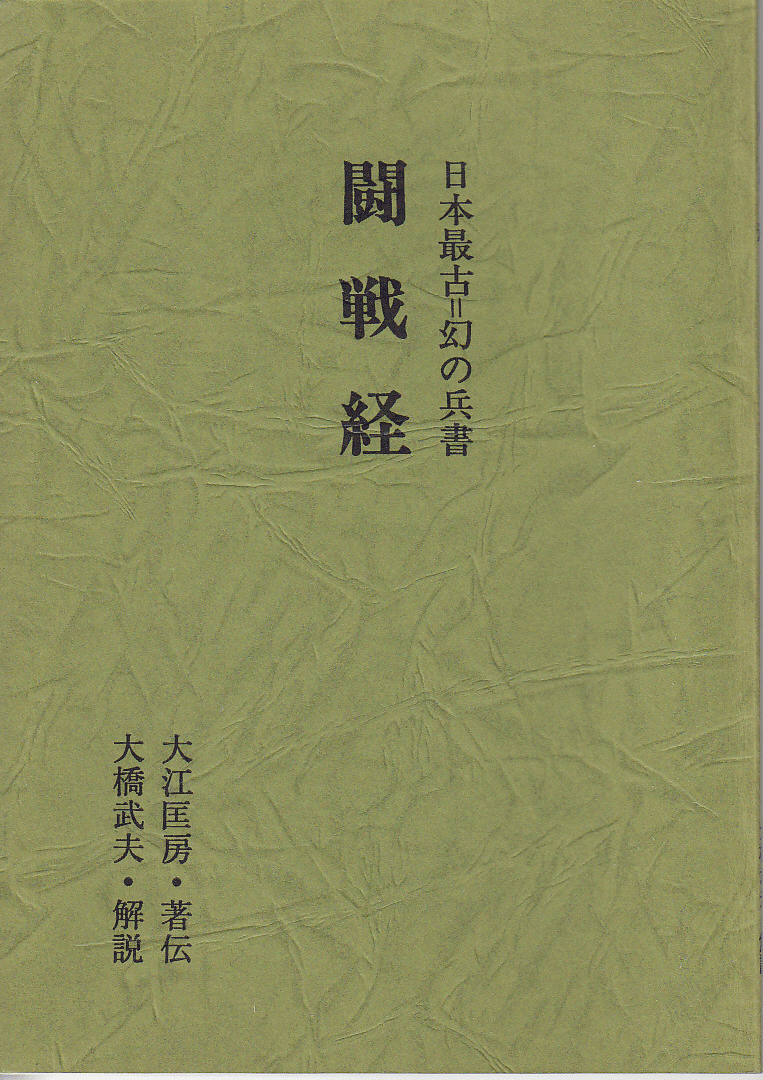
「闘戦経」を世に出すようになった経緯
「闘戦経」は幸いにして先覚の士により、明治にいたってその存在が確められ、海軍兵学校の手に移るにおよんで、昭和九年に木版刷にされたものが若干篤学の士に渡り、さらにその活字化されたものの一本が偶然私(大橋)の所へ来たのである。それは私が東部軍参謀時代の参謀長高島辰彦氏の好意で、戦後「兵法的思考による経営」を研究している私のことを聞かれ、昭和三十七年十月二日に氏秘蔵の一本を下さったのである。氏を中心とするグループはかねてからこの本を研究しておられたようで、篤学の士の訳までついていた。それから十八年後の昭和五十五年十月から、はからずも私はブレーン・ダイナミックス社の前田滋社長の後援により、帝国ホテルと丸の内ホテルで兵法経営塾を開講しているが、熱心な方々が全国から集まられ、ついに昭和五十七年には三年研修生が出ることになった。その結果、今までより高度の兵法研究を行なうことになり、その対象として、中国の「鬼谷子」と日本の「闘戦経」が浮かびあがってきた。いずれも古代の幻の兵書であり、難解である。しかし私は数年前からこの両書を研究していたので、この際これをまとめて本にして教材に使いたいと思い、「鬼谷子」は徳間書店の厚意にあまえて刊行することにし、「闘戦経」は、紙数が少なくて刊行対象にならないため、自費出版をすることに踏み切った次第である。なお大江匡房の文章は現代人にわかりやすいように書き直し、さらに解説と私の考えを付記しておいた。古人の序文に「将来、天機秀発して、後世、しかるべき人に知られるのを待つのみ」とあるが、この八百余年も前の人の悲願が今達成の機を得ることになるかと思えばまことに感慨無量であり、また筆をとる者としてまことに冥利につきる思いがする。なお、私は暗号解読も同様の苦心をして勉強したが、まだまだ不十分なところが多く、結局、私の仕事は「こんな本がある」ということを世の中に紹介するにとどまったようである。私もまた先人の例にならい、将来いつか達識の士が現れて、この本の主張するところをさらに効果的に活用する途を聞かれんことを期待する。なお、あとがきにある大江元綱の言のように、この本は「熟読永久にして、自然に関を脱するを得べし」であり、わからないところはじーっと睨み、繰り返し読みつづけていれば、日本人であるかぎり、いつとはなしにその意味が脳裡に浮かんでくるものであり、読者の不屈の挑戦を念願する次第である。-- 大橋先生著「闘戦経」を考えるより --
電子書籍
「兵法 小澤様問対」
兵法塾外伝・平成 令和
小澤様 !
ありがとうございます。
電子書籍として上・中・下
公開させていただきます。
電子書籍 2024.01.16
| 「兵法 小澤様問対」 | ||||||
| 「兵法小澤様問対」上 | 「兵法小澤様問対」中 | 「兵法小澤様問対」下 | ||||
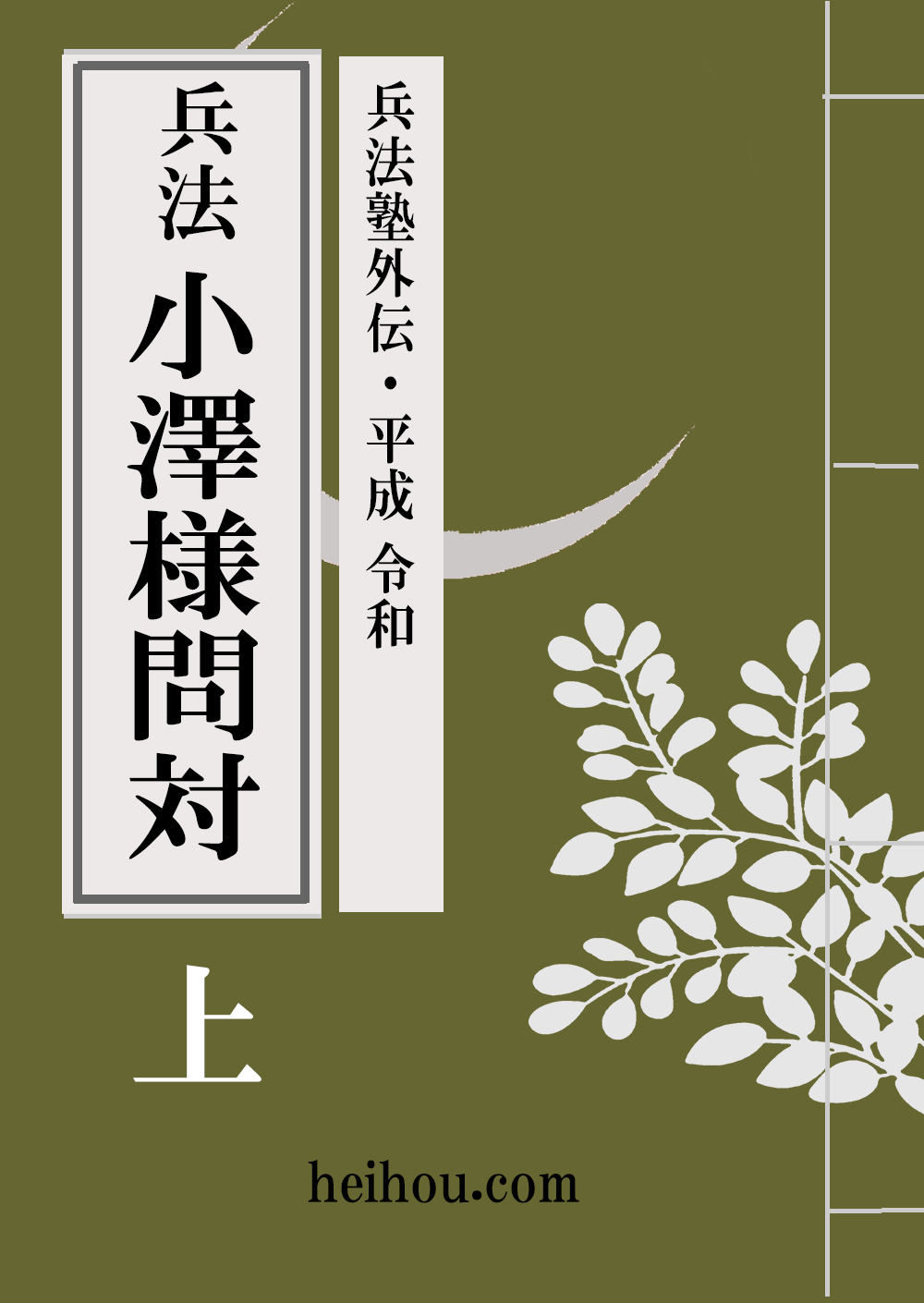 |
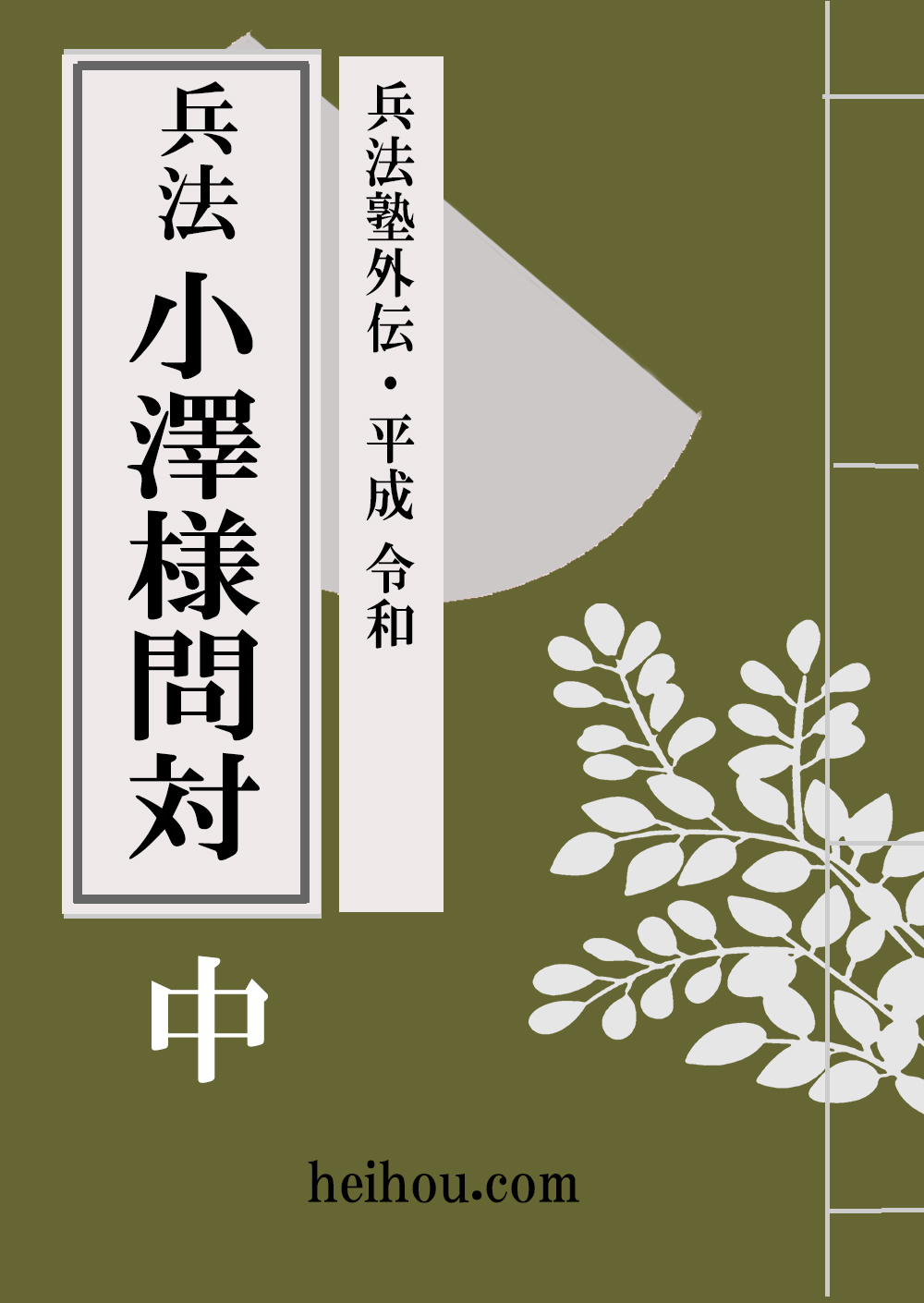 |
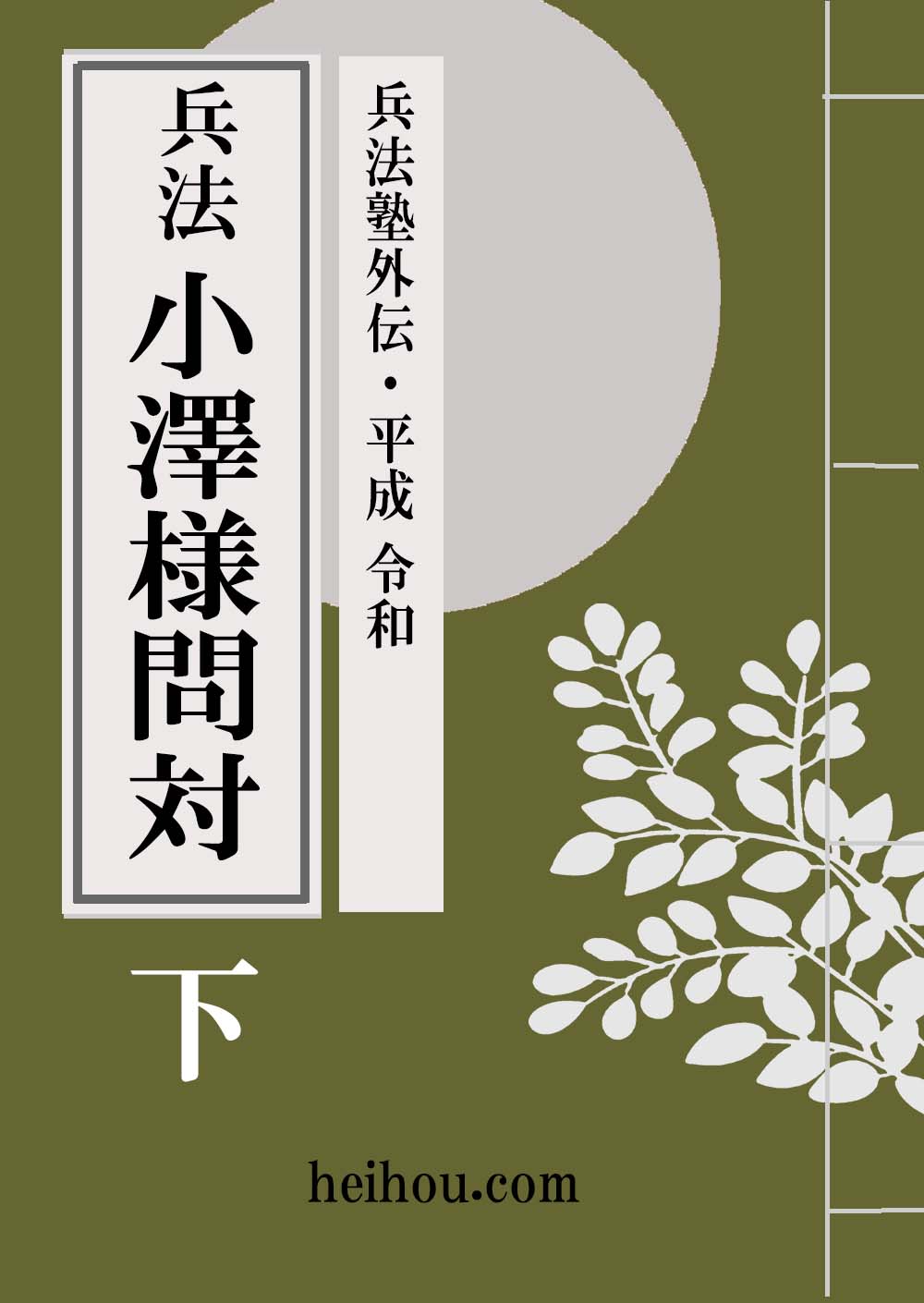 |
||||
「兵法 小澤様問対」上・中・下
(兵法塾外伝 平成・令和)
2009年の3月14日に初めて「小澤様」からの掲示板への書き込みがあり、その都度、拙いご返事をお返ししてきましたが、いつの間にか14年も経過して、世相も時代も大きく変化してしまいました。その時勢に応じた大橋武夫先生、武岡淳彦先生の著書やエピソード及び古典、ビジネス書をテーマにした「小澤様」との掲示板での対話が日々研鑽の証となり、個人的にも人生の貴重な足跡となりました。2013年頃より大橋先生の「お形見の書籍」を電子書籍として作成させて頂いていましたが、この度、「兵法塾・掲示板」での「小澤様」との兵法に関するやり取りを、保存と編集をかねて電子書籍として公開させていただきます。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜れば幸甚でございます。
■ 兵法 小澤様問対 上
【9】~【59】2009(平成21)年3月14日~2010(平成22)年6月26日
■ 兵法 小澤様問対 中
【60】~【115】2010(平成22)年7月28日~2013(平成25)年2月17日
■ 兵法 小澤様問対 下
【116】~【178】2013(平成25)年3月3日~2023(令和5)年1月5日
2023年12月
heihou.com
(ヘイホウドットコム)編集・著者
Amazonアソシエイトで著書の一部をご紹介します
| 兵法経営塾 | 統帥綱領入門 |
3 |
4 |
| 戦いの原則 | マキャベリ兵法 |
7 |
8 |
| ピンチはチャンス | 新釈孫子 |
11
|
12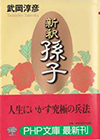
|
| 日本陸軍史百題 | 兵法と戦略のすべて |
15
|
16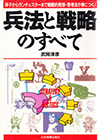
|
| リーダーとスタッフ | 孫子の経営学 |
19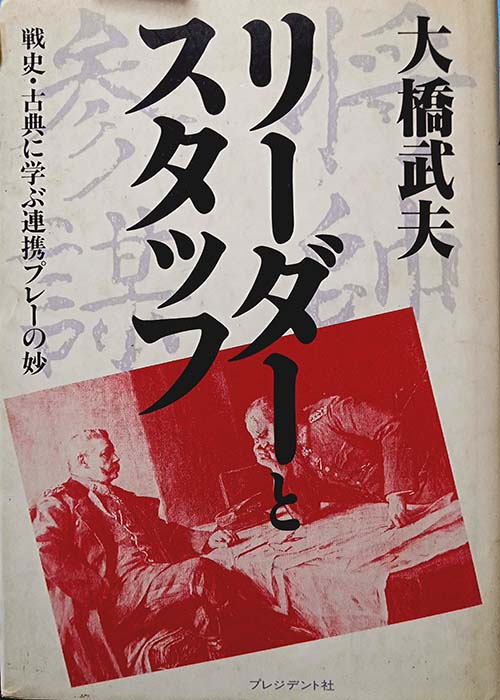
|
20
|
| まんが 孫子の兵法 | まんが 兵法三十六計 |
23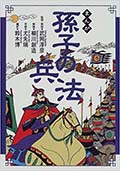
|
24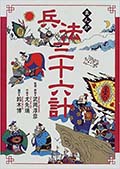
|
| 兵法 項羽と劉邦 | 絵で読む「孫子」 |
27
|
28
|
| 名将の演出 | 兵法 三国志 |
31
|
32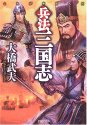
|
| 兵法 徳川家康 | 状況判断 |
35
|
36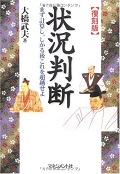
|
| 人は何によって動くのか | 兵法 孫子 |
39
|
40
|
| 経営幹部100の兵法 | 図解兵法 |
43
|
44
|
| 戦略と謀略 | クラウゼウィッツ兵法 |
47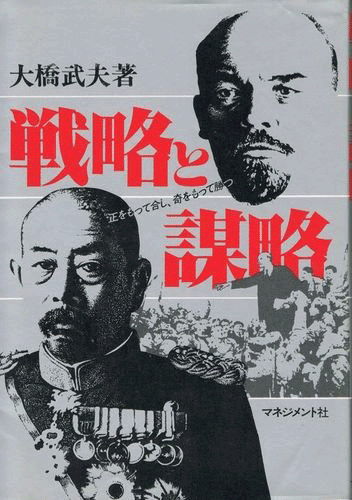
|
48
|
| 兵法・ナポレオン | 参謀総長・モルトケ |
51
|
52
|
| チャーチル | 攻める-奇襲桶狭間 |
55
|
56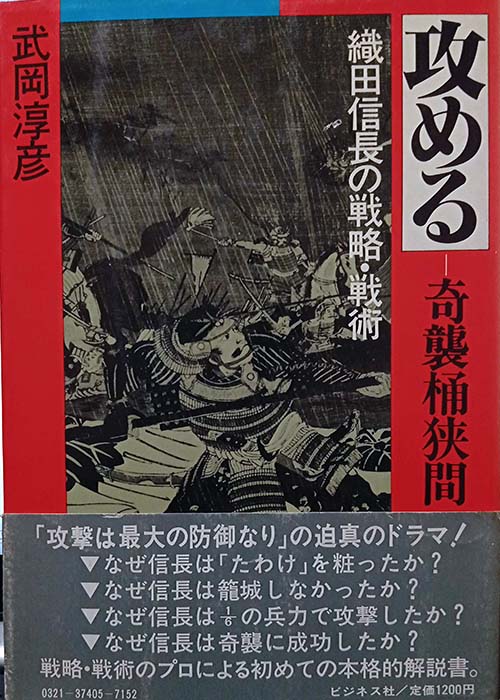
|
| 図解指揮学 | 戦国合戦論 |
59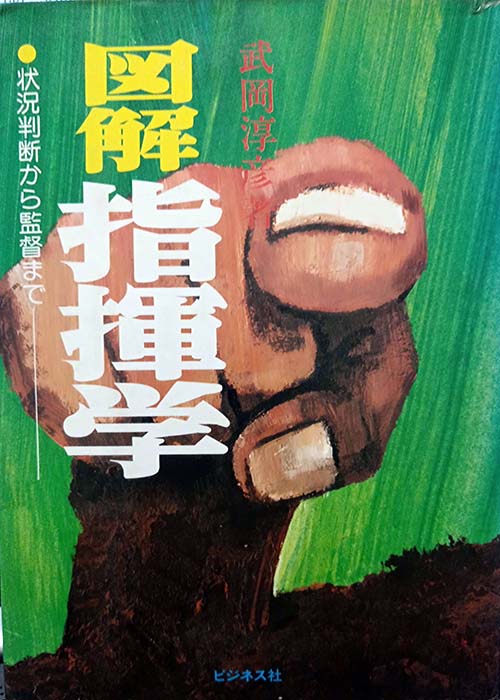
|
60
|
| 必勝状況判断法 | 正攻と奇襲 |
63
|
64
|
| 兆候を読む! | ビジネスマンの兵法ゼミナール |
67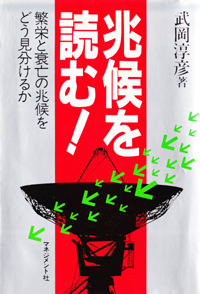
|
68
|
| 孫子一日一言 | リーダーシップ孫子 |
71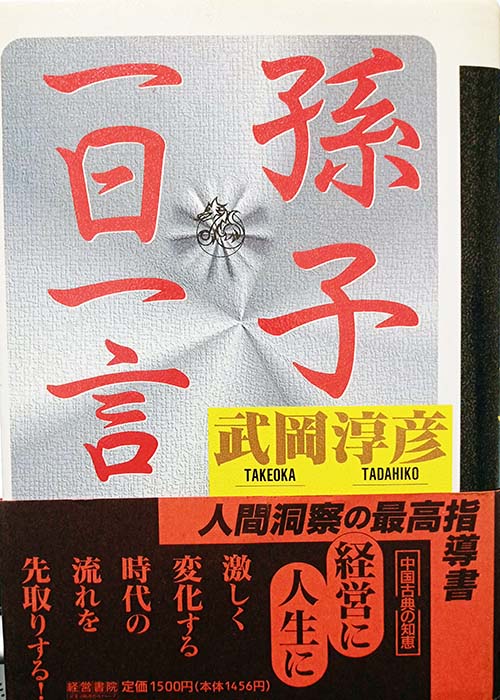
|
72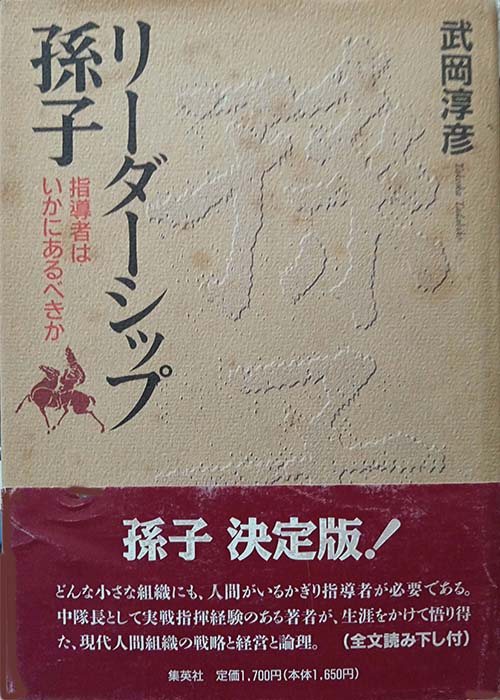
|
| 「孫子」を読む | 湘桂作戦体験記 |
75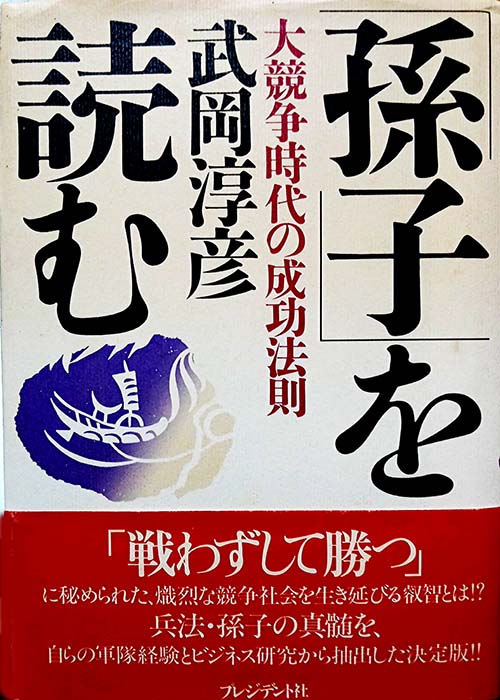
|
76
|
| 初級戦術の要諦 | 方面隊運用序説 |
79
|
80
|
| 統帥綱領 | 作戦要務令 |
83
|
84
|
| 戦争論・解説 | 兵書研究 |
87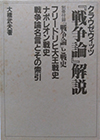
|
88
|
| 図鑑兵法百科 | 兵法で経営する(初版) |
91
|
92
|
| 兵法で経営する(復刻) | スマートに運転する上・下 |
95
|
96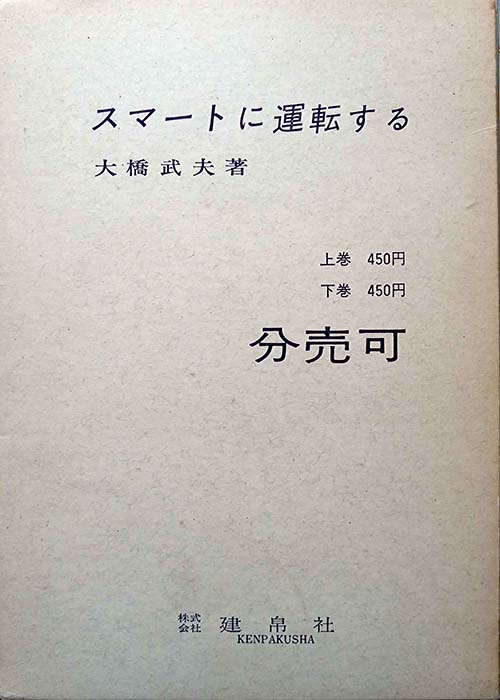
|
| 兵法三十六計 | 鬼谷子 |
99
|
100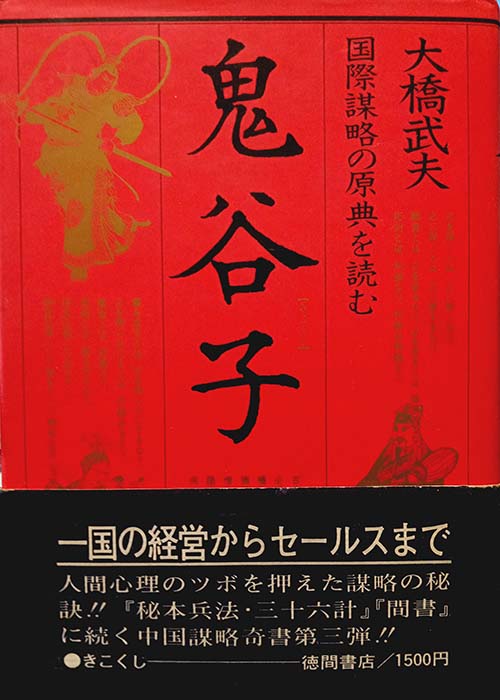
|
| 謀略 | 決心 |
103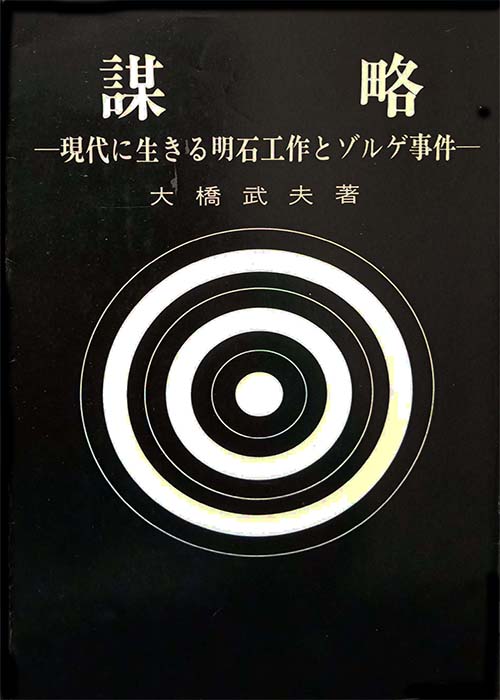
|
104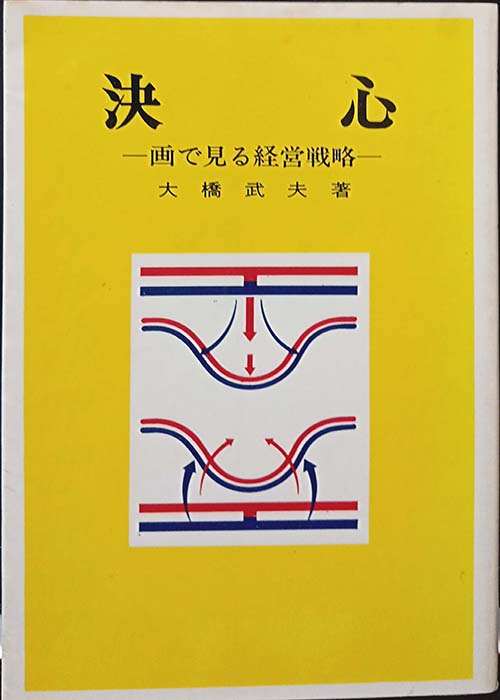
|
| 千に三つの世界 | 兵法小澤様問対・上 |
107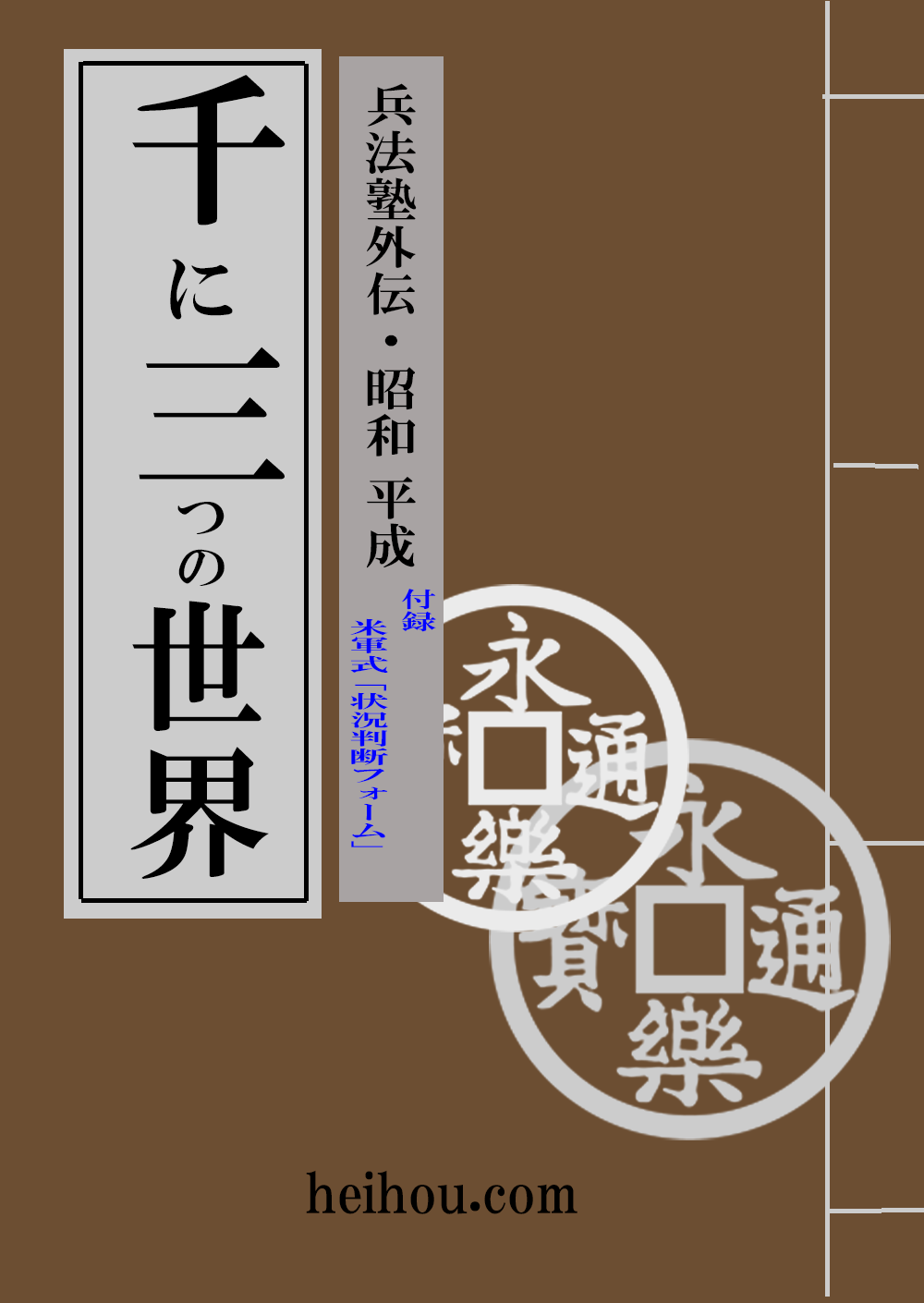
|
108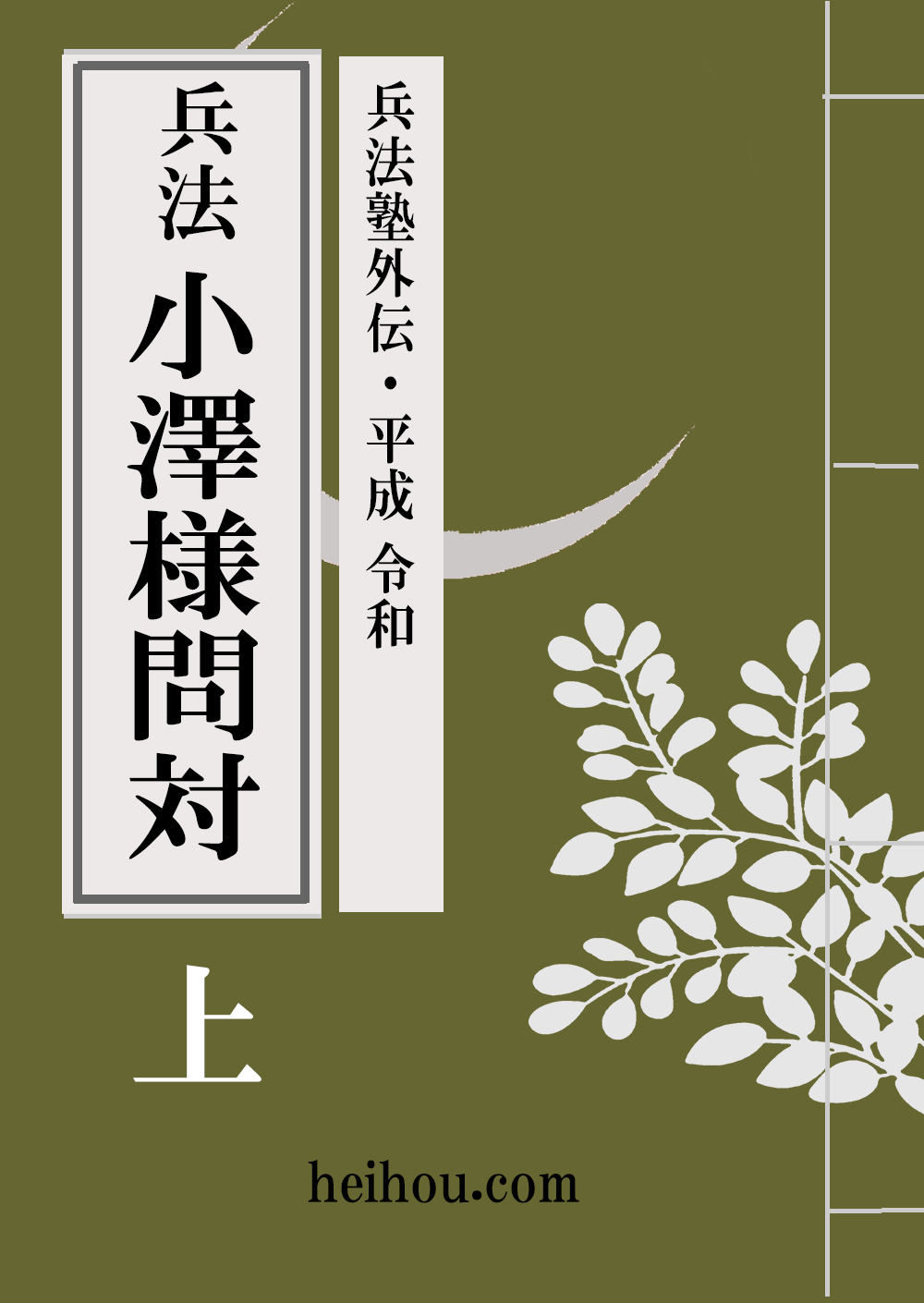
|
| 兵法小澤様問対・中 | 兵法小澤様問対・下 |
111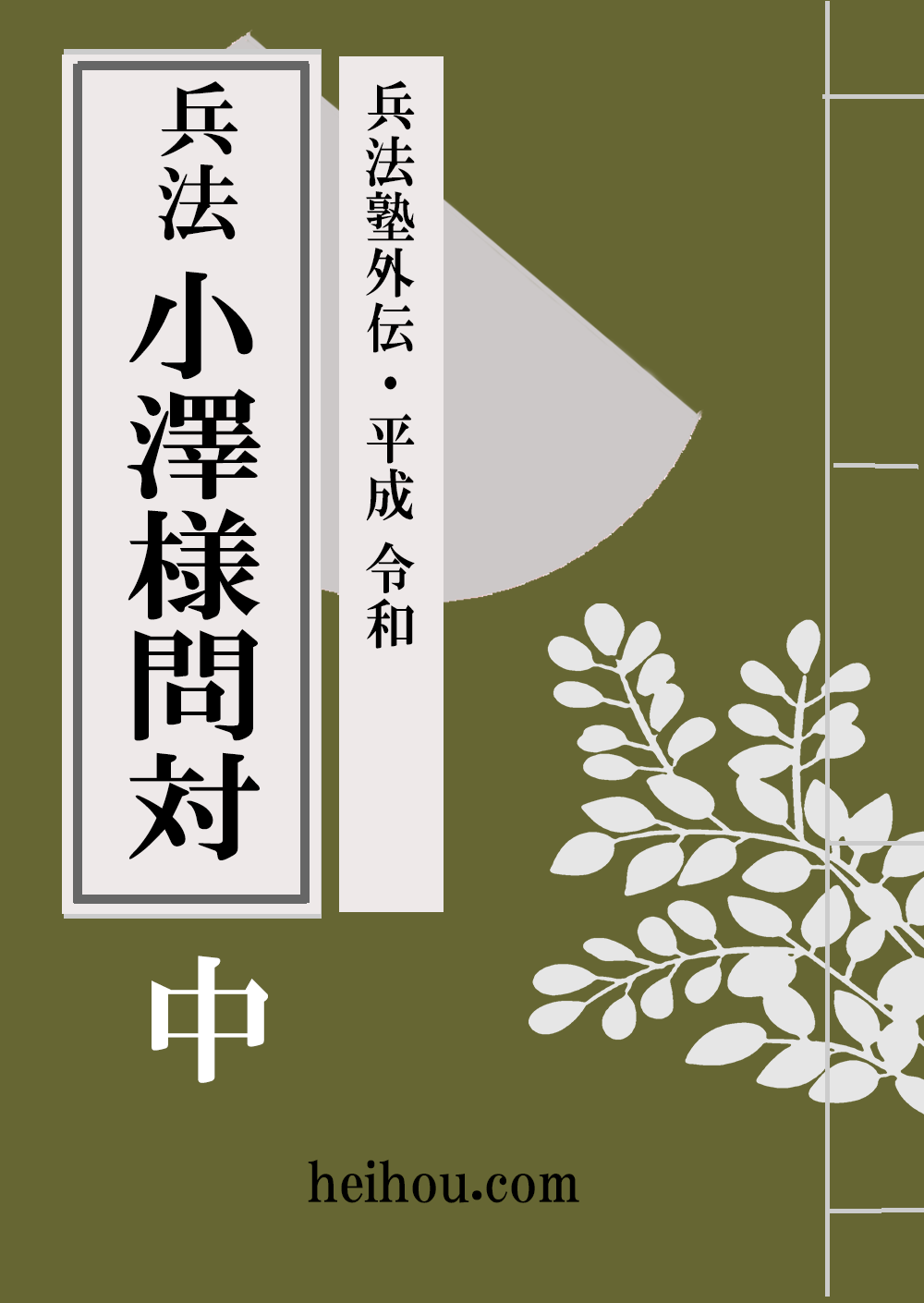
|
112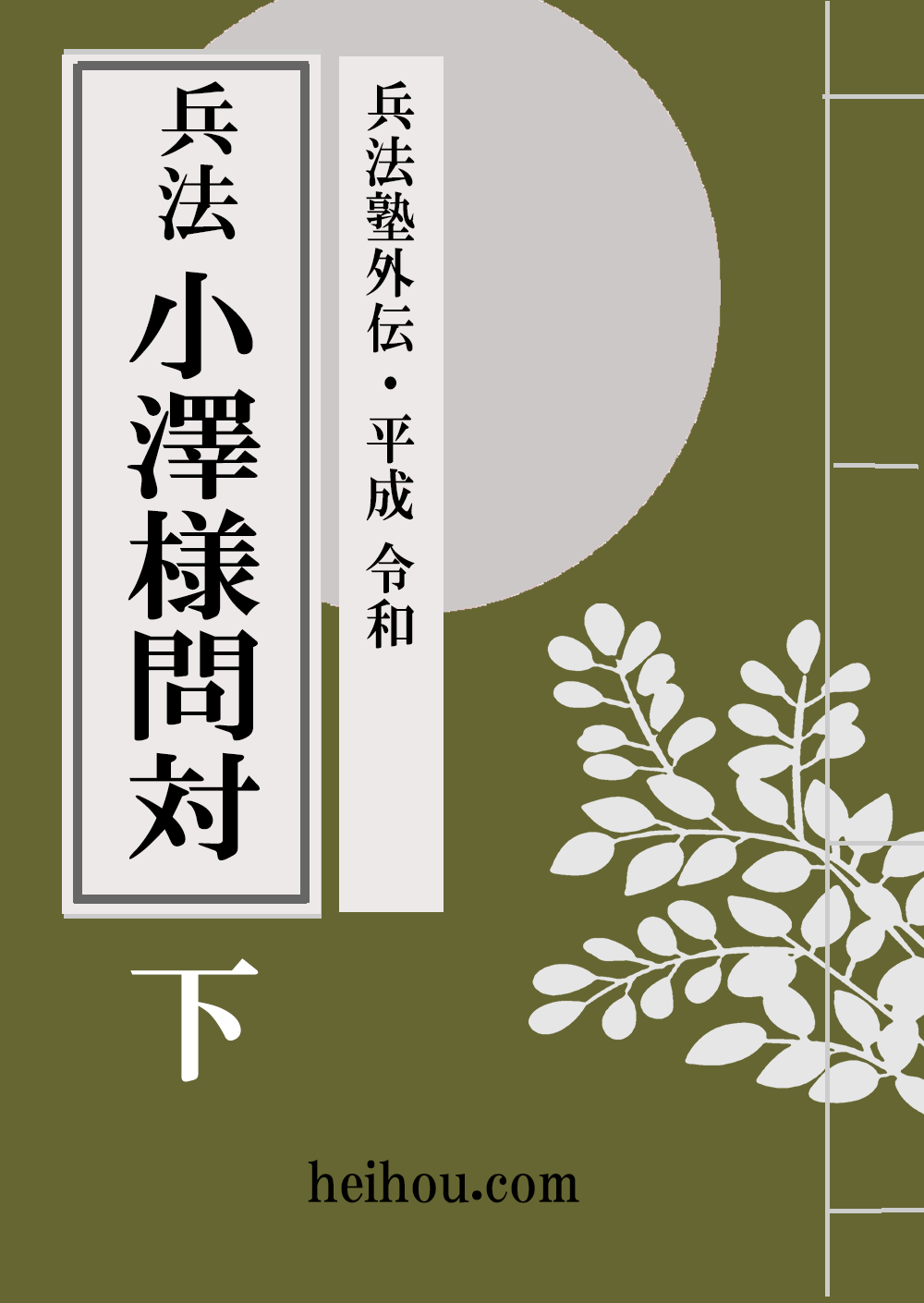
|
©2022- https://www.heihou.com/mobile/All rights reserved.